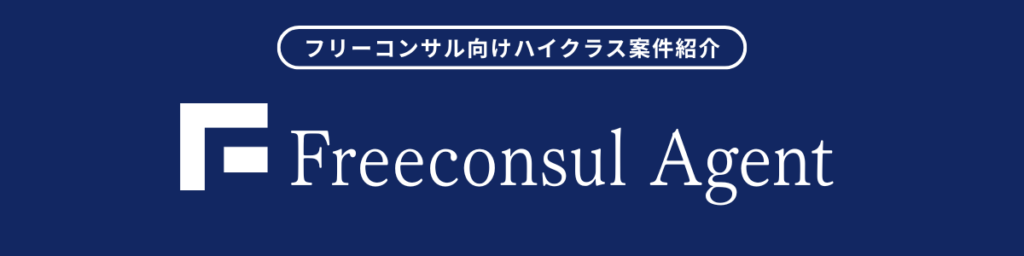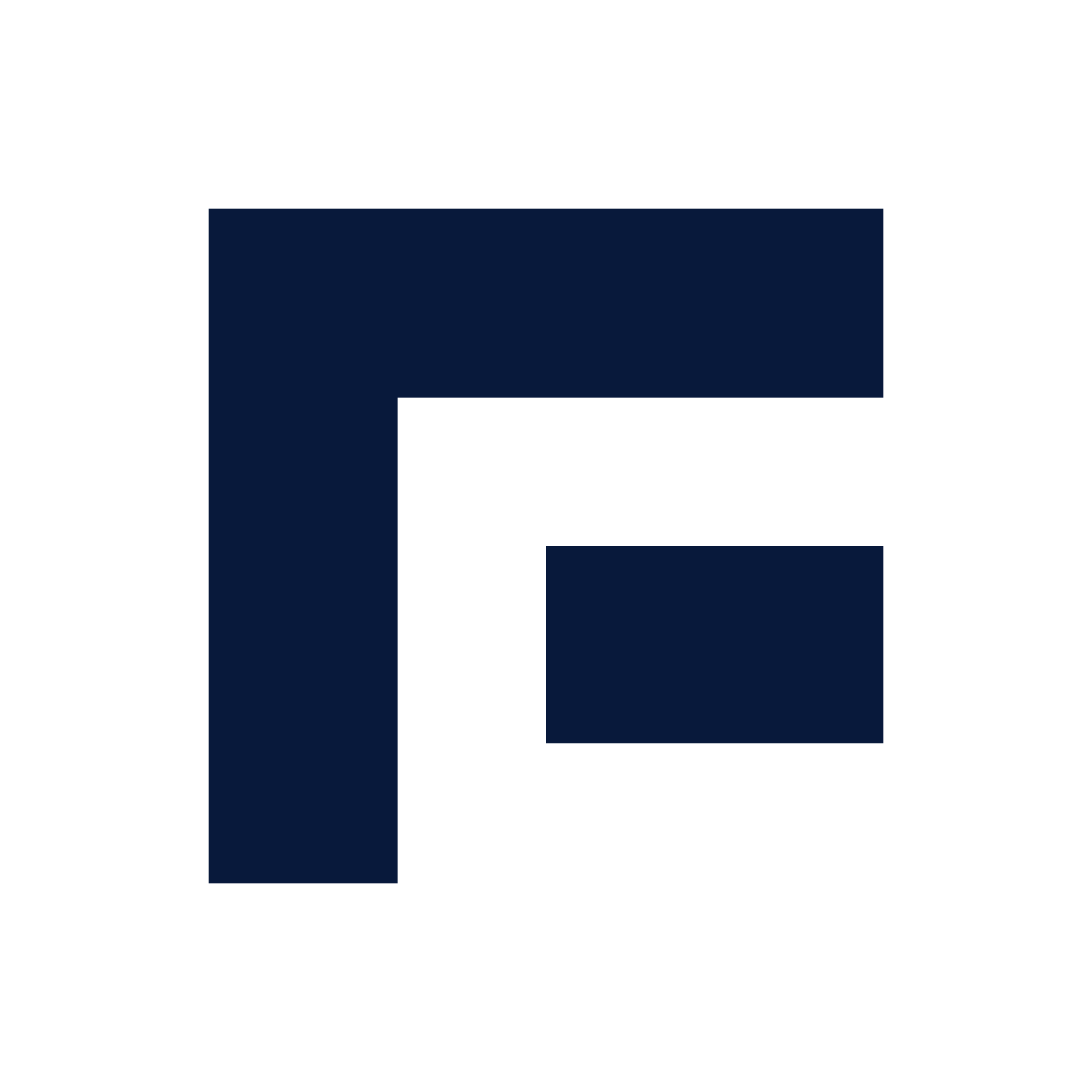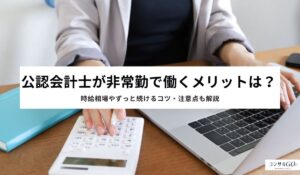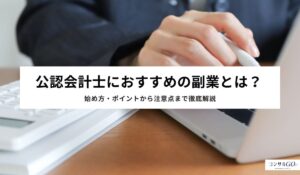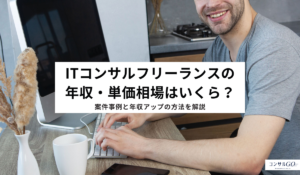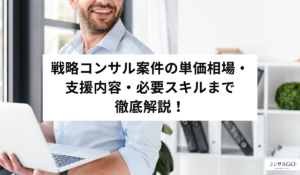コンサルティング事業に身を置いている方々にとって、起業をすることも一つの選択肢です。
「これまで培ってきたスキルや経験を活かして、起業をしてみたいが自信がない」
「失敗が怖く、なかなか一歩踏み出せない」
といった方も多いのではないでしょうか。
しかし、いつまでも行動を起こすことができなければ、起業や独立は夢物語で消えていくことでしょう。
そこで、この記事では、コンサルティング業で起業したい方に向けて、具体的な起業方法など解説していきます。
また、起業に失敗しないコツや役立つ資格、案件獲得のマッチングサイトも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
フリーコンサル向けおすすめ案件紹介サービス4選
| サービス名 | 特徴 |
|
|
業界最大級の案件数!報酬180万円を超える案件が500件以上。 フルリモートや稼働率が低い案件など、豊富な案件を保有。多様な経歴のコンサルタントを積極採用 |
 プロコネクト プロコネクト |
新規案件多数!戦略・業務・IT領域で毎月300件以上の案件を取り扱い |
|
案件掲載数9,300件以上!プライム案件多数だから月額200万円以上の高額案件もあり! 独自のネットワークを通じ他社にオープンになっていない案件を最短1週間で参画可能 |
|
|
平均単価193万円!DX・デジタル案件に特化。 コンサルファーム・大手SIer・大手ソフトウェア会社出身者におすすめ |
関連記事>>フリーコンサルにおすすめ案件紹介エージェント
コンサルタント起業のメリット

ここでは、コンサルティングで起業することのメリットにつてい見ていきましょう。
以下のメリットについて詳しく解説していきます。
起業のハードルが低い
実は、コンサルタントとして起業することは、一般的にイメージされるほどハードルが高いものではありません。
むしろ、他の業種と比べても比較的始めやすい部類に入ります。というのも、コンサルティング業は基本的に自分一人でも始めることができ、特別な設備や大きな初期投資が必要ないためです。
例えば、製造業や飲食業のように物理的な店舗や機材を用意する必要がなく、パソコンとインターネット環境さえあれば、すぐにでも事業をスタートすることができます。
起業の第一歩としては、まず「個人事業主」として開業届を提出するだけでOKです。開業届は税務署で簡単に手続きでき、必要書類も最小限で済みます。行政手続きにかかる時間も短く、費用も無料であるため、想像以上にスムーズに始められるでしょう。
特別な資格が必要ない
「コンサルタントとして起業をするなら、資格がいるのでは?」と考える方も多くいらっしゃるかもしれません。
もちろん、スキルアップや顧客の信頼を獲得するために経営や金融に関する資格や業界に特化した資格を取ることは重要ですが、起業するために取得しなければならない資格はありません。
今までの業務経験を通して自身が学んできたコンサルティングノウハウを武器にして、起業することが可能です。
ただし、取得していた方が顧客に安心感を与えられる資格も存在しますので、後の章で詳しく解説します。
利益率が高く安定しやすい
コンサルティング事業は「無形商材」を扱うため、商品原価がほとんどかからず、非常に高い利益率を実現しやすいビジネスです。
必要な費用も書籍代や資料作成などに限られ、薄利多売になることは少ないでしょう。
コンサルタントとして起業した直後は実績や知名度の不足から売上が不安定になることもありますが、初期費用や運営コストを抑えられるため、他業種と比べて金銭的リスクが低く、持続しやすい点が魅力です。
地道に信頼を積み重ねていくことで、安定した売上や継続的な契約にもつながりやすく、独立後の事業として現実的で有望な選択肢といえるでしょう。
コンサルタント起業のデメリット

ここまでは、コンサルタント起業におけるメリットをお話ししてきました。一方で気になるのは、デメリットです。コンサルの独立はメリットだけとは限りません。
コンサルタント起業のデメリットとしては、例えば以下のようなものが挙げられます。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
参入するカテゴリによっては競合が多い
コンサルティング業で起業する際には、まず自分がどの分野に参入するのかをしっかりと見極めることが非常に重要です。選ぶ領域によって、競合の数や市場の成熟度が大きく異なるためです。
例えば、ITコンサルティングの分野で起業する場合、競争の激しい市場に飛び込むことになります。AIやDX(デジタルトランスフォーメーション)といった注目分野では需要も大きい反面、提供者側も多いため、差別化が不可欠です。
同様に、経営コンサルタントとして起業するケースでも、比較的参入者が多いため、自分の強みや専門性を明確に打ち出す工夫が必要になります。
一方で、法律などの専門知識を要する分野や、競合が少ないニッチなテーマに特化したコンサルティング事業を展開すれば、激戦区を避けつつ独自のポジションを築くことが可能です。
集客に労力がかかる
コンサルタントとして起業するうえで、見落とされがちなデメリットの一つが「集客の難しさ」です。
いくら経験やスキルを持っていたとしても、それを必要とする相手、つまり“顧客”がいなければ、起業後に存続が難しくなってしまいます。とくに立ち上げ初期は知名度も実績も限られているため、仕事の受注が不安定になりがちです。
そのため、起業後に優先的に行わなければならないのが、集客です。
しかし実際には、目の前の業務に追われる中で、未来の顧客へのアプローチにも時間とエネルギーを割かなければならず、非常にバランスが難しいのが現実です。特に一人や少人数で事業を運営している場合、この“営業と実務の両立”が大きな負担と感じられることも少なくありません。
コンサルタント起業の方法

ここからは、具体的にコンサルタント起業の方法を解説していきます。
個人事業主として開業するのであれば、お住まいの地域にある税務署で、開業届を出すことによって完了しますが、法人を設立する場合はまた異なる手続きが必要になってきます。
本記事では、法人を設立することを前提としたコンサルティング起業の方法を解説していきます。
流れとしては以下の通りです。
まず、事業計画書の作成から解説していきます。
事業計画書作成
事業計画書は、事業を始めるうえで必要になってくる重要な書類です。
事業計画書が無くとも、個人事業主として開業可能ですが、法人設立を考える場合は、資金調達や今後のビジネスを考えたうえで、事業の財務計画、運営の方針を具体的に記載することが求められます。
事業計画書は、資金を集める際に活用できるだけでなく、自分自身のビジネスが今後どのように展開していくかの道しるべにもなります。
ただし、あまりにも現実離れした事業計画を作成しないよう注意しましょう。
資金調達
基本的には、金融機関からの資金調達がメインとなります。
ここでは、上記で作成した事業計画書をもとに、金融機関の担当者と打ち合わせを行います。金融機関側が、事業に対して返済の余地がある、リターンを得られると判断した場合に初めて資金調達が可能です。
また、資金調達をする金額も現実的なものを考えておきましょう。申請額が高額すぎると、事業計画書と内容が合わずに資金調達が失敗に終わる可能性があるためです。
その他の資金調達方法としては、補助金や助成金の利用、投資家から出資を受けるというパターンも考えられます。
まずは、金融機関からの融資を受けることを進めながら、補助金や助成金各種の手続きを並行して行いましょう。
会社設立
ここでいよいよ会社設立となります。
会社設立に関しては、司法書士など専門家に依頼して、会社の登記などをするのが最も効率的でしょう。
司法書士へ依頼するときの費用相場は、登記以外にも「登録免許税」や「定款承認」などの手数料、「印紙税」など、合わせて15万円くらいから30万円弱となっています。
コンサルタントとして起業した際の集客方法
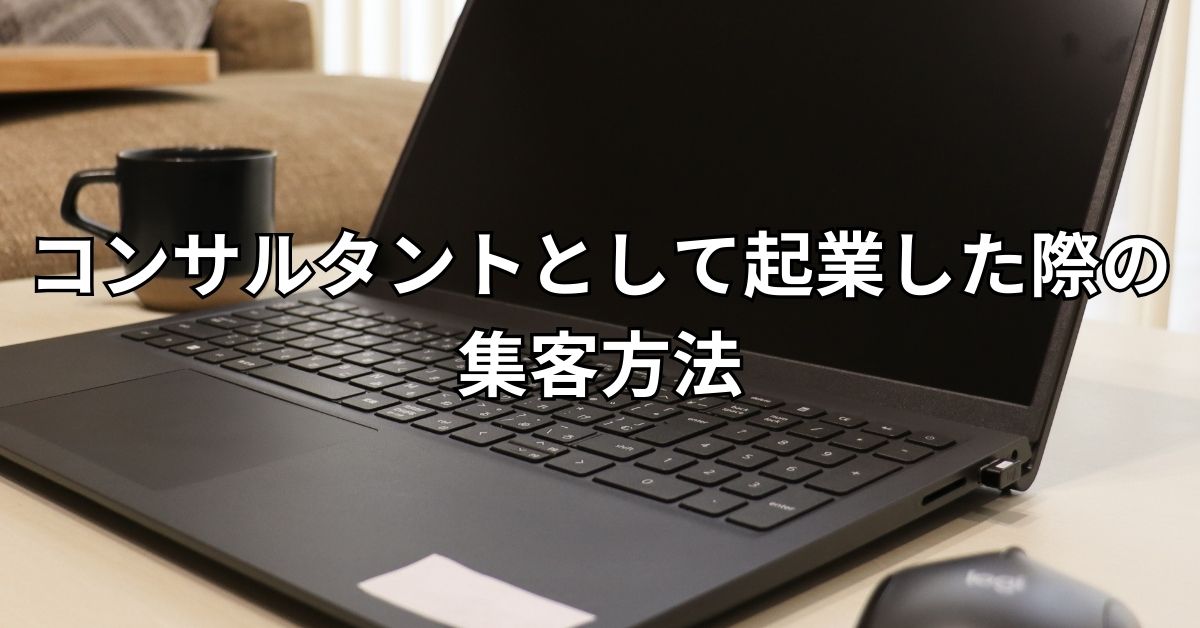
コンサルタントとして起業した際の具体的な集客の方法としては、例えば以下のようなものが挙げられます。
- 前職でつながりのある企業へアプローチする
- 顧客になりうる企業をリサーチしてアプローチする
- SNSの利用して潜在顧客へアプローチする
- セミナーを開して集客をする
- クラウドソーシングサイトを利用する
それぞれの方法にはメリット・デメリットがあり、自分の強みや得意分野と照らし合わせて最適な手段を選ぶことが重要です。
たとえば、前職でのつながりを活かす方法は、信頼関係がすでに構築されているため成果に結びつきやすい一方で、リーチできる企業数が限られる可能性もあります。SNSの活用はコストを抑えて広範囲にアプローチできる反面、コンテンツの発信力や継続性が求められるでしょう。
また、セミナー開催やクラウドソーシングの活用などは、自身の専門性をアピールできる良い機会となります。自分の専門性や提供価値をどのように伝えるかも、集客においては大きなポイントです。
集客方法はさまざまですが、まずはどの領域でビジネスを進めるのかをしっかりと念頭に置いて、然るべき場所で顧客獲得を目指しましょう。
コンサルタント起業で失敗しないためのコツ
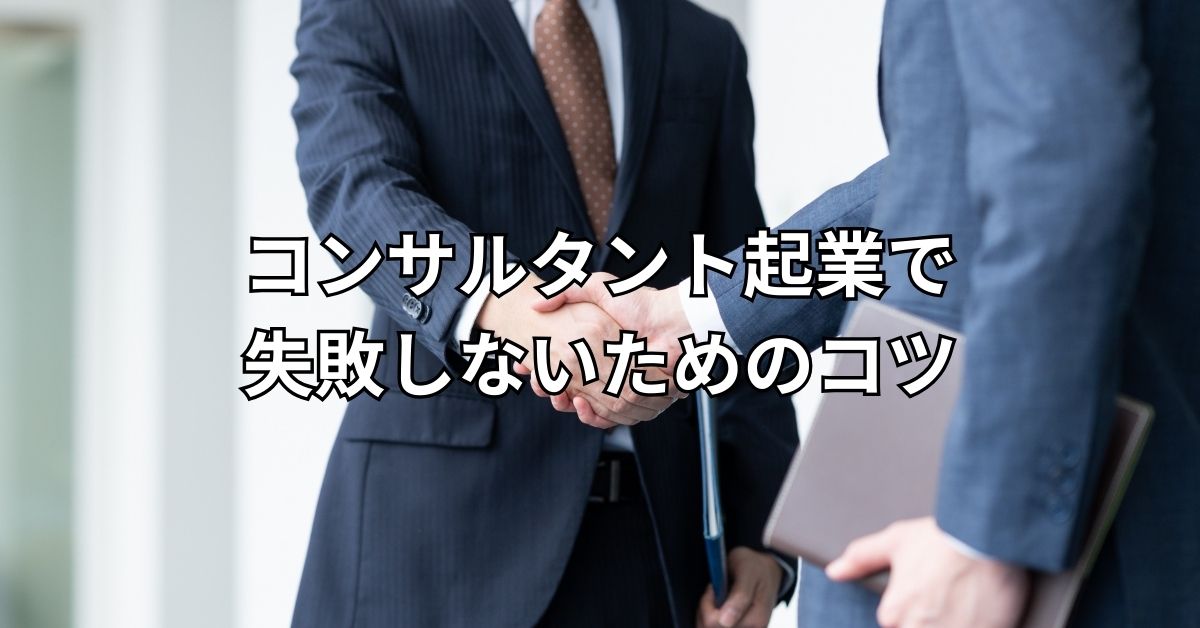
ここからは、コンサルティング起業をする際、失敗をしないためのコツをいくつか紹介していきます。
口コミを活用する
コンサルティング業で独立、または起業をする際は、顧客から信頼を獲得している証明となる「口コミ」の活用がキーポイントとなります。
コンサルティング起業を果たしても、顧客から信頼されていなければ仕事を見つけるのに苦労するでしょう。良い口コミをもらうためには、顧客に対し、いかに「丁寧かつ親身になって接しているか?」という点が重視される傾向です。
さらに、良い口コミを見た人が、顧客になってくれたり、既存顧客が新たな顧客を紹介してくれたりする可能性もあります。
そうした良い循環を生み出せれば、自然に顧客が集まる状態を作れ、集客費用を抑えることも可能です。
過去の経歴からの人脈を活かす
コンサルティング起業をする場合、これまで築き上げてきた人脈を積極的に活用するのがおすすめです。
現職の職種にもよりますが、取引先の人脈や個人的につながっている人脈を、独立時にそのまま潜在顧客としてアプローチをするところから始めてみましょう。
そういった方々に対し、普段から真摯に接していれば、応援する意味も込めて、独立後に協力をしてくれる可能性が高くなります。
無料相談から始めるのも選択肢
起業直後は、実績を積み信頼性を高めていくことが重要です。そのために無料相談を実施するというのも一つの選択肢ではないでしょうか。
実績のないコンサルタントに報酬を支払って仕事を依頼するというのは、顧客からしてもやはりハードルが高いものです。実際に相談を受けて信頼してもらえれば、口コミなどで次の仕事に繋がる可能性もあります。
限定的に無料相談をおこなったり、キャンペーンとして低価格で実績を積んでいくのもよいでしょう。
コンサルタント起業の選択肢
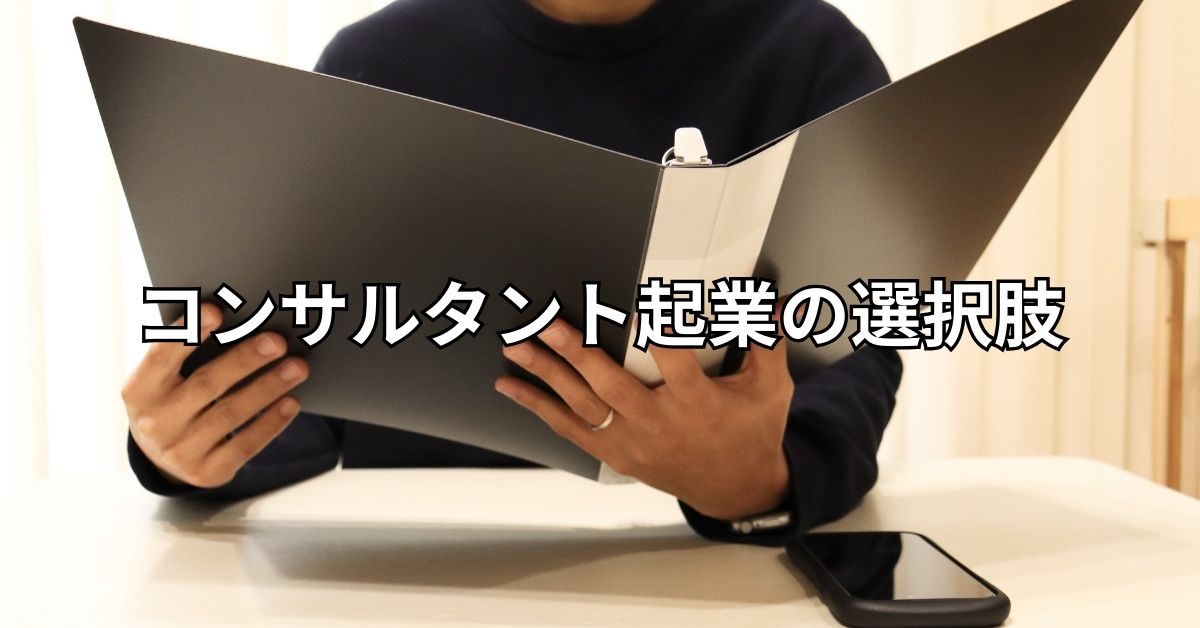
実際にコンサルタント起業を考えた時に、どのような起業方法があるのかについて、例を出して解説していきます。
起業を考えている方の経験や能力によって、独立方法はさまざま存在します。
副業から始め個人事業主として起業
まずは、本業を離職せずにフリーコンサル副業として起業する場合です。
コンサルティング業は、仕事をする場所が自由に決められ、昨今の「リモートワーク推奨」の流れが、さらに働き方を柔軟にしているため、本業があっても副業として始めやすいといえます。
隙間時間を利用して、コンサルティング事業を立ち上げることも可能です。
コンサルティング会社から独立
すでにコンサルティング会社に勤務している方にとって、独立はスムーズに進めやすい選択肢です。現職で培ってきた専門・業界知識、プロジェクト経験はもちろんのこと、築いてきたクライアントとの信頼関係やネットワークは、独立後の基盤として大きな強みになります。
また、実務経験を通じて、「どのような課題が多く発生するのか」「どのような提案が顧客に響くのか」といったノウハウが自然と蓄積されているため、ゼロからスタートする場合と比べて、立ち上げ初期の不安も少ない傾向にあります。
さらに、退職前にある程度準備期間を設けることで、独立後のサービス内容や営業戦略を具体化したり、旧知のクライアントへアプローチしたりと、事前の土台作りも可能です。タイミングや業界との関係性を見極めながら進めれば、比較的リスクを抑えた形での独立が実現できます。
弁護士や税理士などの士業から独立
弁護士、税理士、社会保険労務士などのいわゆる“士業”と呼ばれる専門職の方々が、独立してコンサルティング業を行うケースも増えています。こうした資格保有者は、特定の法律知識や制度に精通しているという強みがあり、一般のコンサルタントでは対応が難しい領域にも踏み込むことが可能です。
さらに、士業資格自体が信頼の証ともなり、初対面の相手でも安心感を持ってもらいやすい点も独立時のメリットのひとつです。既存の顧問契約などをベースにコンサルティングサービスを付加したり、専門性の高いセミナーや顧問契約を組み合わせることで、高付加価値なビジネスモデルを構築することも可能です。
このように、士業としての経験と資格を最大限に活かせば、特定分野に特化した専門コンサルタントとして、各企業へアプローチすることができます。
起業におすすめのコンサルティングの種類
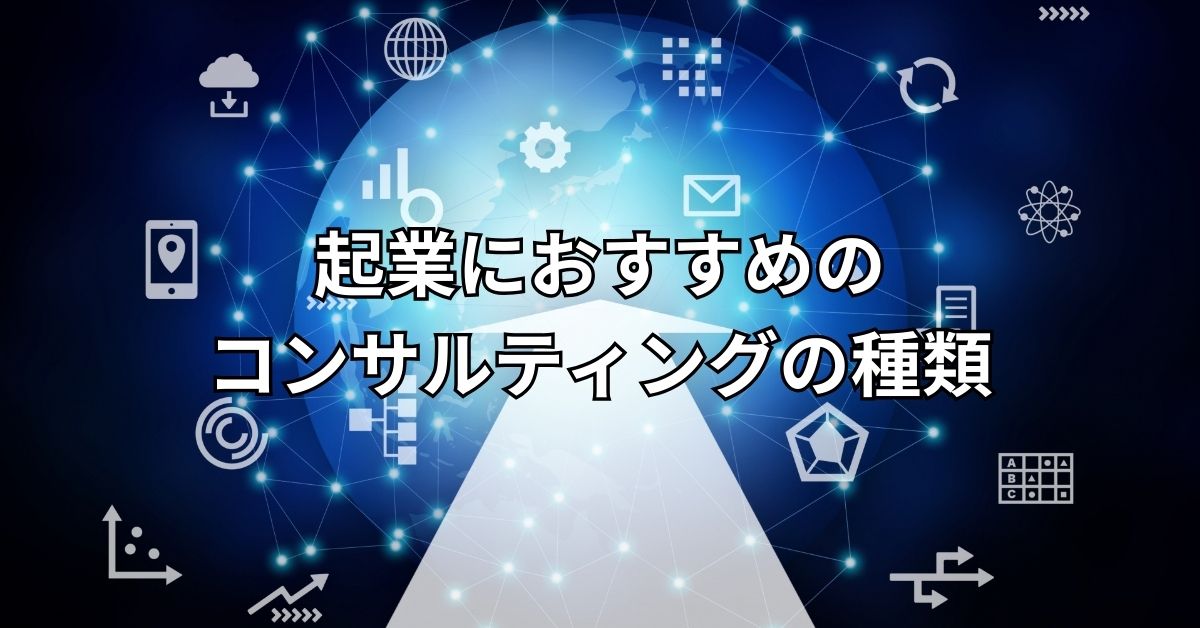
起業におすすめのコンサルティング業としては、例えば、以下のようなものが挙げられます。
それぞれ詳しく解説していきます。
Webコンサルタント
Webコンサルタントは、対象の企業が運営しているウェブサイトについて、効率的かつ価値のある運用方法や集客の導線を作るコンサルタントです。
Webコンサルタントは単にウェブサイトの見た目を整えるのではなく、ユーザーの導線設計やコンテンツ戦略、SEO対策、広告運用など、サイトを「成果を出す営業ツール」として活用するための包括的な支援を行います。
具体的な業務内容としては、クライアント企業のウェブサイトのデザインや運営方法についてのコンサルティングを実施するなどが挙げられます。
クライアントにとって「サイトをどう使えばビジネスが伸びるのか」を明確にし、それを実現するためのサポートを行う、非常に実務的かつ価値の高いコンサルティング領域と言えるでしょう。
ITコンサルタント
ITコンサルタントのフリーランスは、対象企業における、部署横断的な社内システムの開発から運用、メンテナンスに至るまでを請け負います。
特に、企業の基幹システムの入れ替えや新しい業務システムの導入に際しては、最適なシステム構成やベンダーの選定、導入スケジュールの策定まで、プロジェクト全体の舵取りを任されることもあります。
また、システムを導入して終わりではなく、導入後の社員向けのレクチャーやマニュアル作成、運用ルールの整備といった“定着支援”まで実施するというのもITコンサルタントの業務です。
ITは業界問わず必要不可欠なインフラとなっているため、フリーランスのITコンサルタントには、技術力だけでなく、現場と経営の両視点から課題を見つけ、解決策を提示できる総合的なスキルが求められます。
戦略コンサルタント
戦略コンサルタントは、対象企業の経営戦略立案を始め、現状の経営方針や体制を調査して課題を抽出します。
その課題に対して、アドバイスを行い、会社に利益をもたらすのがコンサルタントの業務です。
主に、クライアント企業の経営陣と常にコミュニケーションをとり、利益最大化を支援する重要な役割を担っています。クライアントの内部事情に深く入り込み、論理的な分析力と実行力のある提案が求められるため、高いスキルと責任感が必要です。
そのため、戦略コンサルタントとして独立を目指す場合は、コンサルティングファームや大手企業の経営企画部門などで実際に経営戦略の立案やプロジェクト推進に携わった経験が重視される傾向があります。豊富な実務経験と信頼性が、独立後の活動における大きな強みとなるでしょう。
コンサル起業をした人の年収はどのくらい?
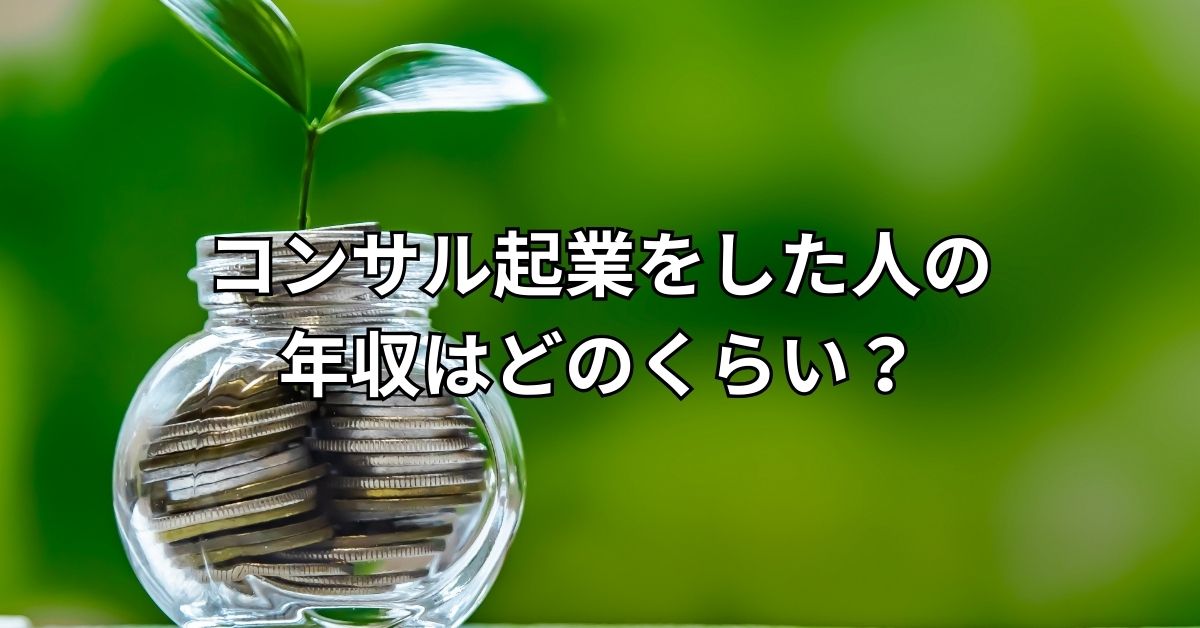
コンサルタントとして起業した場合の年収は、それぞれの実力や抱えるクライアントの規模によっても異なります。
一例として、フリーコンサルタントの案件を取り扱うハイパフォコンサルでは、案件検索画面において月額報酬60~180万円以上までの条件設定が可能です。※1 たとえば、月額報酬が100%稼働で60万円の場合、単純計算で60*12=720万円ということになります。180万円以上であれば、2,160万円です。正社員の令和5年度の平均年収は530万円※2ですので、どちらにせよ高額な年収が期待できます。
なお、先ほど年収はクライアントの規模によっても異なると説明しましたが、規模が大きければよいということではありません。スキル・働き方などによっては、中小規模のクライアントを多く持つことが最良というケースもあります。自身の強みと合致するターゲット層を設定することで、年収を伸ばしていくことも可能でしょう。
参照元
起業直後の案件獲得におすすめのコンサルタント案件サイト
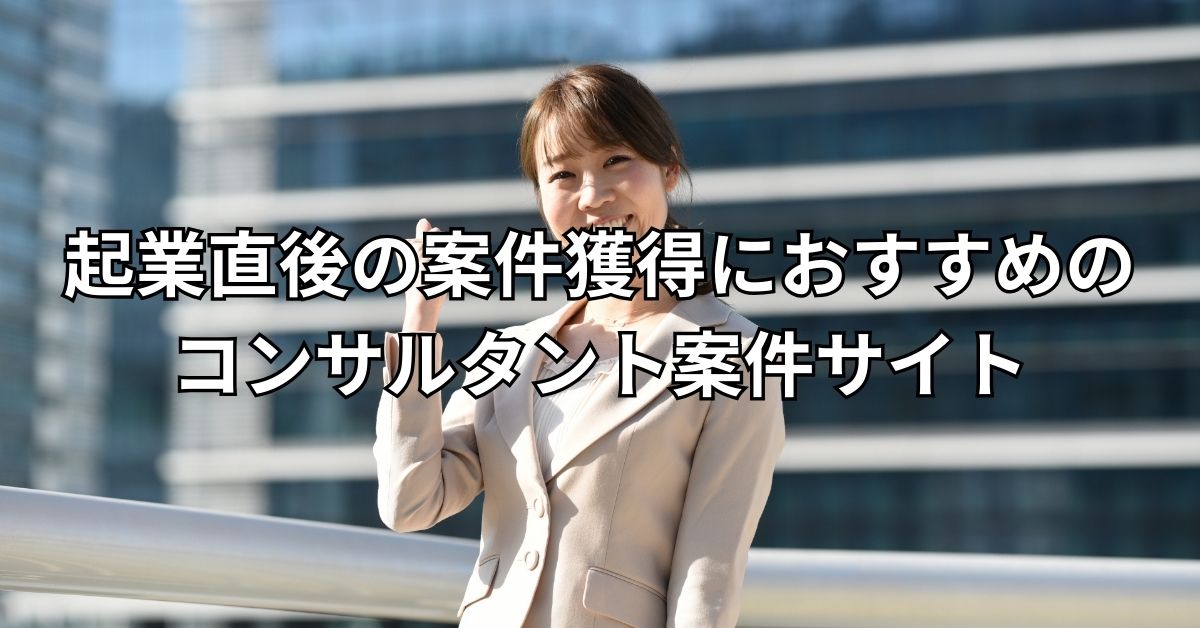
コンサルタントとして独立したばかりの時は、営業がうまくいかないケースもあります。
そんな時は、案件獲得サービスを展開するマッチングサイトの利用がおすすめです。
ここでは以下のサービスを紹介します。
ハイパフォコンサル

引用元:ハイパフォコンサル
- 高待遇案件が多数180万円以上の報酬も可能
- 21年の歴史・全登録者数46,000名以上の信頼
- 業界最速水準の翌月15日払い
ハイパフォコンサルは、東証グロース市場に上場している、INTLOOP社が展開するマッチングサービスです。
首都圏を中心とした全国エリアを対象に、フリーランスとして働くコンサルタントに案件を紹介しています。これまで21年にわたって多数の案件を紹介してきた実績があり、多くのフリーランスコンサルタントから高い信頼を得ているのも強みです。
IT業界はもちろん、金融、医療、不動産・建築にいたるまで、豊富な求人を取り扱っています。登録者数の年代は30代~40代が最も多く、若手から中堅のキャリアを持つフリーランスから支持を得ているサービスです。
さらに、フルリモートや一部リモートの案件も豊富に取り扱っており、柔軟な働き方を希望するコンサルタントにも対応しています。
また、支払いも月末締め、翌月15日の短い支払いサイクルを実現しているのも特徴です。支払いが早いのは、フリーランスコンサルタントになりたての方にはありがたいポイントと言えます。
| 運営会社 | INTLOOP株式会社 |
|---|---|
| 公式サイト | https://www.high-performer.jp/consultant/ |
| 公開求人数 | 8,273件(2026年1月18日現在) |
| 得意領域 | ITコンサル、PM・PMO、SAPなど |
デジタル人材バンク

- DX構想や中期経営計画支援など、経営直結の上流案件が中心
- 企業との直接契約により、平均月単価は201万円(税抜)と高水準
- 独立初期のキャリア相談や資金繰りなど、起業支援にも対応
デジタル人材バンクは、戦略・業務・IT領域における上流工程に特化したフリーランス向けのマッチングサービスです。
大手企業におけるDX推進や新規事業構想、中期経営計画の策定支援など、コンサルタントとしての経験を活かせる「構想・設計」フェーズの案件が中心。起業後に即戦力として実績を積むには最適な案件環境が整っています。
案件は企業との直接契約が中心で、平均月単価は201万円(税抜)と高水準を誇ります。収入面での安定性があるため、起業初期のキャッシュフロー不安を和らげつつ、ビジネス基盤を整えることができます。
また、登録者への支援はマッチングにとどまらず、独立初期のキャリア相談などにも対応。運営には大手コンサルファーム出身者が多数在籍しており、実務や働き方への理解も深いのが魅力です。
案件獲得だけでなく、長期的に起業を軌道に乗せたい方は、デジタル人材バンクのような相談できるエージェントを活用することをおすすめします。
| 運営会社 | 株式会社クラウド人材バンク |
|---|---|
| 公式サイト | https://consultant.digital.hr-bank.co.jp |
| 公開案件数 | 非公開(2026年1月18日現在) |
| 職種 | 戦略、ITコンサルタント |
ProConnect(プロコネクト)
- クライアントからの入金を待たずに9営業日で報酬が支払われる仕組み
- 平均単価170万円/人月のハイクラスな案件
- 連絡スピードの速さや高品質な対応も強み
ProConnect(プロコネクト)は、戦略・業務・IT領域で毎月300件以上の新規案件を取り扱う案件紹介サービスです。
書類審査をパスした人材だけが受け取れるハイクラス案件は月平均単価170万円と高額で、報酬の支払いも9営業日と業界最速水準であることが特徴です。
案件の内容としては業務効率化やシステム開発支援、プロジェクトの立ち上げといったものが多く、基本はクライアント先への出社とリモートを併用した働き方がメインとなります。一部フルリモートの案件も存在します。
ハイスキルを活かして高単価で仕事をしたいという方におすすめのサービスです。
| 運営会社 | 株式会社WorkX |
|---|---|
| 公式サイト | https://pro-connect.jp/ |
| 公開求人数 | 223件(2026年1月18日現在) |
| 主な求人職種 | 業務効率化・標準化支援 RPAコンサルタント など |
コンサルタント起業の際に役立つ資格

コンサルティング起業をするために、必須の資格はありません。
ただし、経営戦略や事業に直接関わるような資格を持っていれば、クライアント企業から信頼されるなどメリットもあります。
例えば以下のような資格が挙げられます。
- 社会保険労務士:労働者の観点から、労務問題や組織コンサルティングなどに役立つ
- 中小企業診断士:経営課題の発見と改善、事業拡大のための知識を活かせる
- 公認会計士:独占業務を持ち、会計に関するコンサルティングに重宝される
- 税理士:税務関連のコンサルティングで必要とされる
- 経営学修士(MBA):経営全体の見通しや、マーケティングなど会社を運営する上で必要なアドバイスが可能
- キャリアコンサルタント:人材に寄り添ったコンサルティングができ、組織強化にもつなげることが可能
コンサルタント起業に関する疑問・Q&A
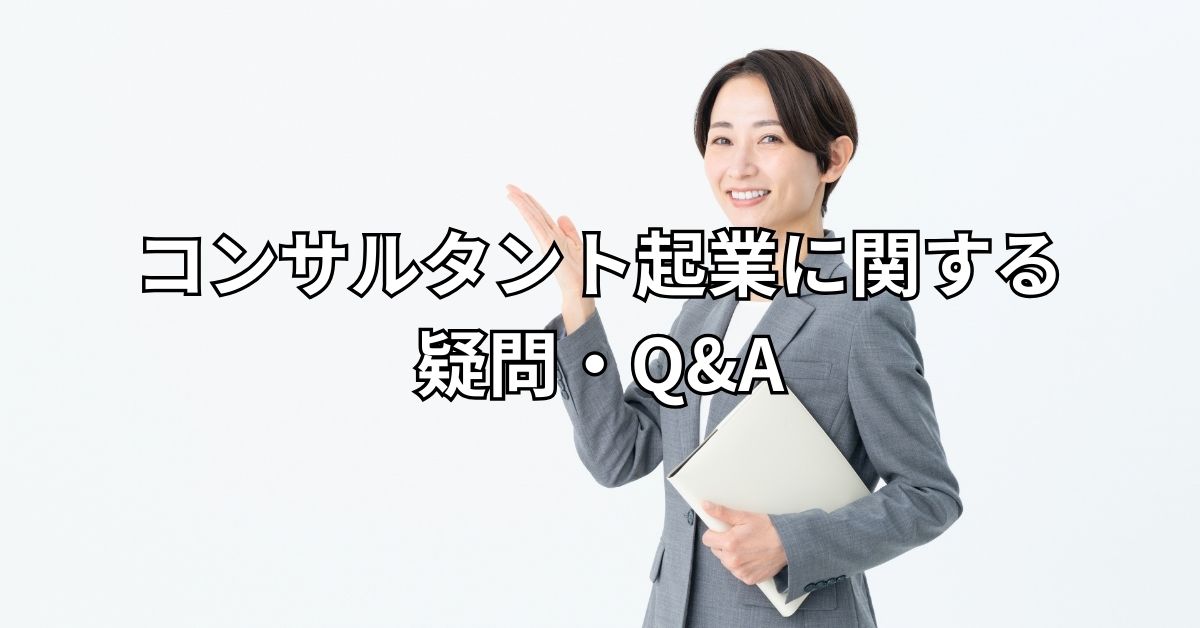
これからコンサルタント起業を予定している方にとって、気になる疑問がありますよね。
ここからはよくある疑問に関して、Q&A形式にて解説していきます。
コンサルタントとして起業するにはいくらぐらい必要?
コンサルタント起業をする際に掛かる費用ですが、どのくらいの規模にするかで、コストはさまざまです。
例えば、自宅で開業するのであれば、名刺を準備する数百円から数千円ほどでスタートできます。
ただし、事務所を構えて起業する場合は、事務所の賃料なども考慮しておく必要があります。また、法人として起業する場合は、法人登記費用が15~25万円程度発生します。ホームページ制作などを依頼する場合も外注費がかかるため、考慮する必要があるでしょう。
コンサルタント起業は、個人と法人どちらがおすすめ?
コンサルタントとして独立する際、まず悩むのが「個人事業主として始めるか」「法人(会社)を設立するか」という選択です。
コンサルの個人事業主と法人では、それぞれにメリットとデメリットがあります。
それぞれ見ていきましょう。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 個人事業主 |
|
|
| 法人 |
|
|
上記のように、それぞれに一長一短があるため、自分の事業スタイルや収益見込み、将来的な展望を踏まえて選ぶことが重要です。
たとえば、まずはリスクの少ない個人事業主としてスタートし、売上が安定してきた段階で法人化を検討する、というステップを踏むというのも一つの選択肢といえます。
コンサルは何年で辞める人が多いですか?
コンサルは求められるスキルレベルが高く、長時間労働にもなりがちなため、比較的短期間で辞めてしまう人が多いと言われます。また、近年では、キャリアアップのために短期間で転職をするという流れも増えてきています。
1~3年程度で辞めてしまうケースもありますが、反対に5年、10年以上続ける人もいるでしょう。
他の業界・職種と同様に、個人の性格やキャリアプランのほか、配属された部署とどの程度マッチしているかによっても、何年コンサルを続けるかというのは異なります。
コンサルタント起業のまとめ
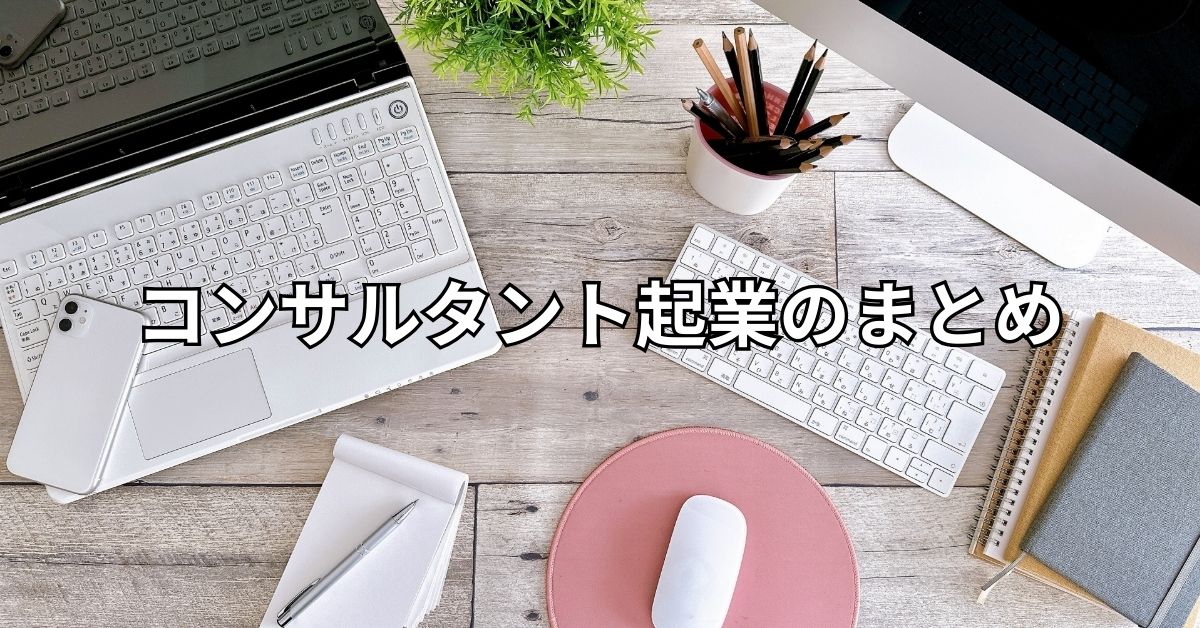
コンサルタントとして独立起業することについて解説をしてきました。
以下が本記事のまとめです。
- コンサルタント起業はハードルが比較的低く初期費用も少なめ
- コンサルティングの内容によっては競合が多くなる可能性もある
- コンサルタント起業直後は過去の人脈や案件サイトを活用するのもおすすめ
- 個人事業主・法人どちらで起業するかは、事業スタイルや計画によって決めるとよい
個人事業主と法人で開業方法は異なりますが、コンサルティング起業は比較的実現しやすいものです。
現在、コンサルティング業界でスキルを磨いており、近い将来、起業を検討している方にとって、本記事が参考になれば幸いです。

監修者:
本多 翔
フリーコンサル株式会社 代表取締役
大学院卒業後、EYアドバイザリー株式会社(現EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング)にてコンサルティング業務に従事。その後、フリーコンサルとして多様なプロジェクトを経験したのち、フリーコンサル株式会社を創業。現在はコンサルタントやハイクラス人材向けに転職・フリーランス案件を紹介する「フリーコンサルエージェント」の運営とともに、大手企業を中心にマーケティングや業務改革支援などのコンサルティング事業を展開している。