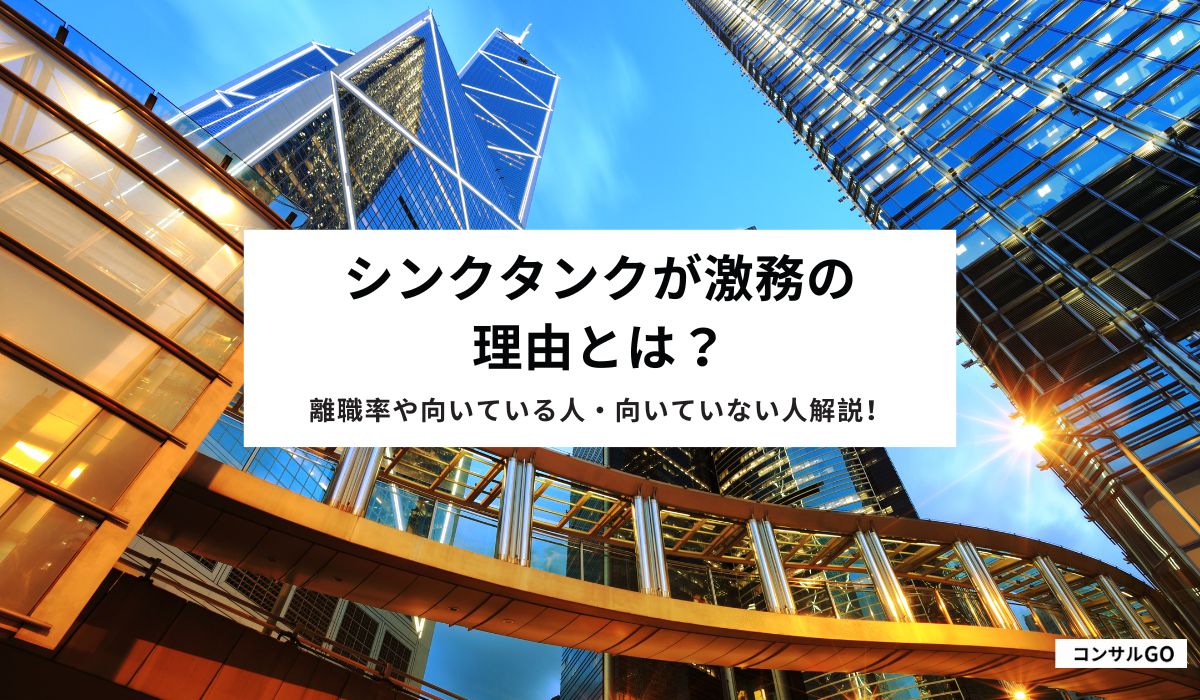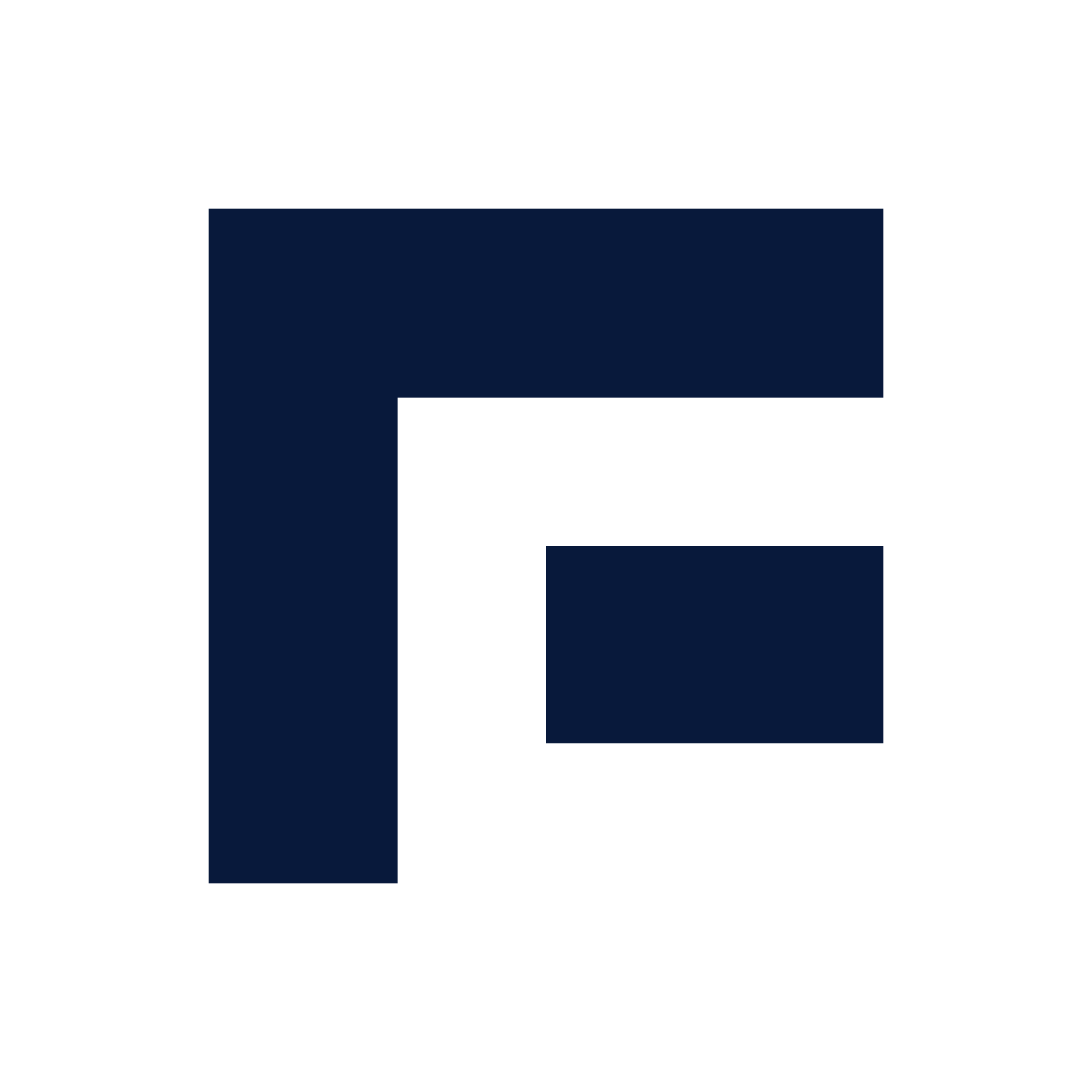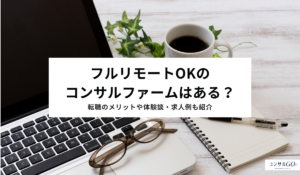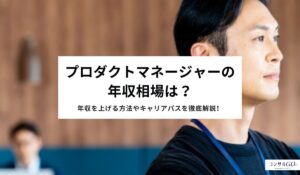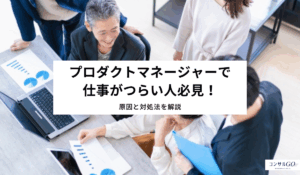「シンクタンクは激務」「離職率が高い」といった話を聞いて、不安を感じている方も多いでしょう。確かに、政策提言や企業向けのコンサルティングを担うシンクタンクの仕事は、高い専門性と迅速な対応が求められ、一般的なオフィス業務とは働き方が大きく異なります。
しかし、業務の実態を正しく理解すれば、自分に合っているかどうかを冷静に判断が可能です。本記事では、シンクタンクが激務の理由や離職率の現状に加え、向いている人・向いていない人の特徴まで詳しく解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
コンサル業界向け
おすすめ転職エージェント
| サービス名 | 特徴 |
|---|---|
 MyVison | 200社以上のコンサルファームとの強固なコネクションで国内に展開するファームほぼすべてに紹介可能。 「面接対策資料」と「想定頻出問答集」に加え、元コンサルタントを仮想面接官とした模擬面接により、実践力を鍛えられる |
 アクシスコンサルティング | 大手ファームの4人に1人が登録する国内最大級コンサル採用・転職支援サービス 未経験からのコンサル転職やポストコンサル、事業会社CxOなど、希望のキャリアパスに応じて幅広い支援が可能。 |
 コンコードエグゼクティブグループ | 日本ヘッドハンター大賞MVP受賞の転職支援サービス コンサル幹部との強固なネットワークでマッキンゼーやBCGなどの「コンサルタント転職」や、コンサル出身者の経営幹部キャリアを支援する「ポストコンサル転職」に高い実績あり |
関連記事>>シンクタンク向け転職エージェントおすすめ

監修者:
本多 翔
フリーコンサル株式会社 代表取締役
大学院卒業後、EYアドバイザリー株式会社(現EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング)にてコンサルティング業務に従事。現在はフリーコンサル株式会社を創業し、コンサルタント・ハイクラス人材向けに転職・フリーランス案件を紹介する「フリーコンサルエージェント」を運営。あわせて大手企業を中心にマーケティングや業務改革支援など、コンサルティング事業も展開している。
シンクタンクは激務?離職率はどれくらいか
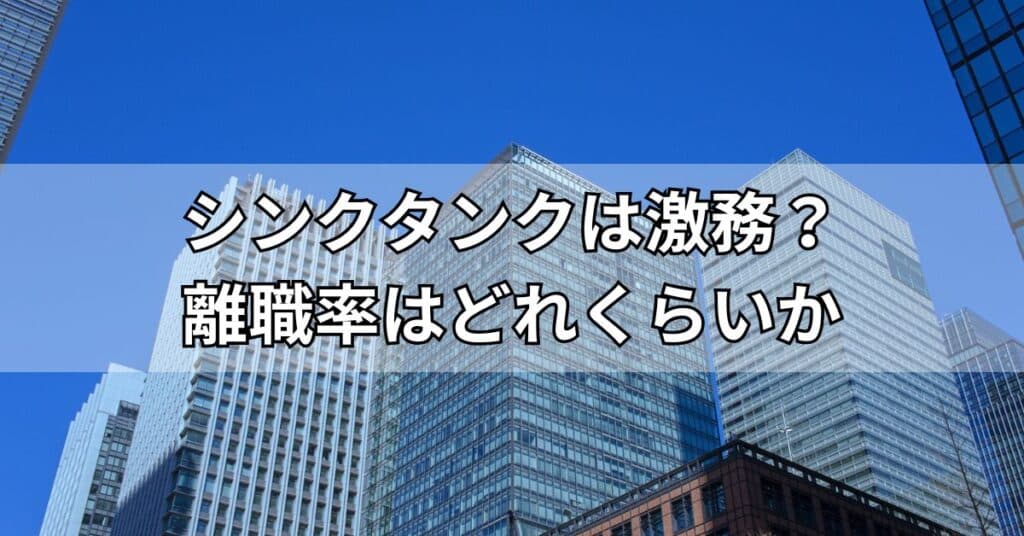
シンクタンクでは専門的な知見や高い分析能力が求められ、日々の業務量も多いため、ワークライフバランスが課題となるケースもあります。
ここでは、実際の労働時間や離職率に関するデータをもとに、シンクタンクの激務の実態を詳しく解説します。
シンクタンク業界の労働時間
シンクタンクの労働時間は企業によって差がありますが、全体的にはやや長めの傾向が見られます。openworkに掲載されている主要シンクタンクの月間平均残業時間を、以下の表にまとめました。
| 企業名 | 月間平均残業時間 |
|---|---|
| 野村総合研究所 | 約45.0時間※1 |
| 三菱総合研究所 | 約40.5時間※2 |
| NTTデータ経営研究所 | 約63.1時間※3 |
| 日本総合研究所 | 約38.5時間※4 |
| みずほリサーチ&テクノロジーズ | 約33.2時間※5 |
上記の通り、月30〜40時間程度の残業が発生する企業が多く、繁忙期にはさらに増える可能性もあります。ただし、柔軟な働き方を導入する企業もあり、労働環境の改善に取り組む姿勢が見られる点は注目すべきでしょう。
参照元
※1openwork「株式会社野村総合研究所」
※2openwork「株式会社三菱総合研究所」
※3openqork「エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所」
※4openwork「株式会社日本総合研究所」
※5openwork「みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社」
シンクタンク業界の離職率
シンクタンク業界における離職率を正確に把握するのは難しいですが、厚生労働省が発表した「令和5年雇用動向調査結果の概況」によると、「学術研究、専門・技術サービス業」の離職率は11.0%※とされています。
この分類にはシンクタンクだけでなく、コンサルタントや研究機関も含まれるため、業界全体の平均的な離職率と捉えることができます。一般的な業種の平均離職率が14.3%であることを踏まえると、やや低めの水準です。
これは、高い専門性や仕事のやりがいに魅力を感じ、長く勤める人が多いことが背景にあると考えられます。
【事例】野村総合研究所の離職率
シンクタンク業界の中でも注目度の高い野村総合研究所(NRI)では、公式サイトにて離職率を明示しています。NRIの最新データによると、自己都合離職率はわずか3.2%※と非常に低い水準です。
この傾向は、働きやすい職場環境や高い報酬水準、そして自己成長を実感できるプロジェクトへの参加機会が影響していると考えられます。離職率が高いとされがちな業界の中では、際立った数字と言えるでしょう。
なお、NRIの企業情報は公式サイトでも確認できます。シンクタンク業界に関心のある方は、こうした具体的な事例を参考にしながら企業選びを進めるのも有効な方法です。
参照元
シンクタンクが激務の理由
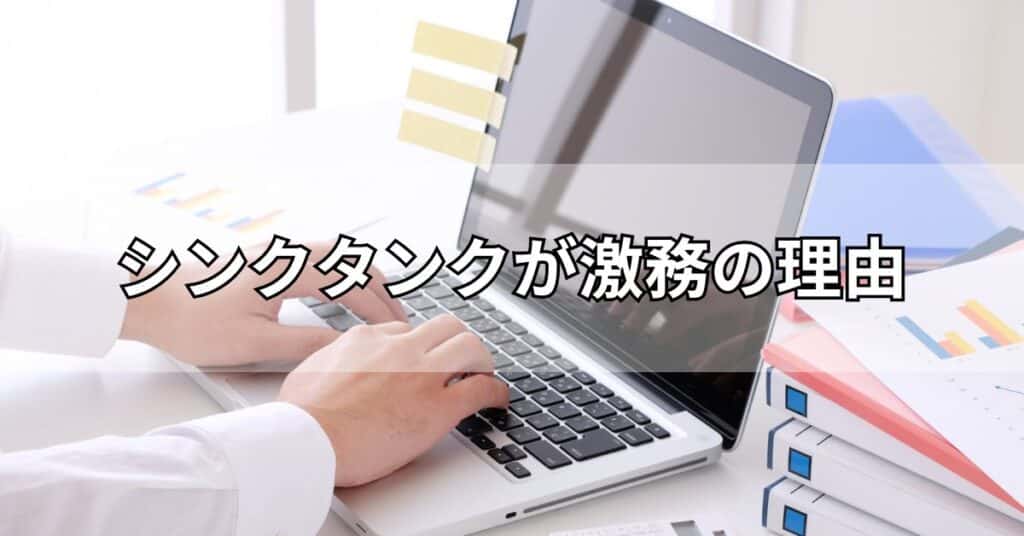
シンクタンクは知的労働の最前線に立つ職種であり、専門性の高い業務をスピード感をもってこなす必要があります。成果が明確に求められる業界のため、業務量や責任の重さは相当なものです。ここでは、シンクタンクが激務といわれる理由について、具体的に見ていきましょう。
シンクタンクは過酷なノルマが設定される
シンクタンクが激務と言われる理由の1つは、個人やチーム単位で明確な成果目標や納期が設定されることが多いことです。
特にコンサルティング部門では、クライアントごとに異なる課題に対して、短期間でレポートや分析結果を提出しなくてはいけません。
納期が延びることはほとんどなく、内容の質も強く求められるため、常に高いプレッシャーの中で業務をこなすことになります。
加えて、評価制度は成果主義の色が濃く、数値や結果で成果を示せなければ昇進や報酬に影響する可能性もあるでしょう。このような背景から、業務に追われる状況が続きやすく、長時間労働が常態化しやすい傾向にあります。
終わらない分析と調査の繰り返し
シンクタンクの業務は、膨大な情報の収集と分析が中心です。市場データの取得や統計処理、先行研究の精読、レポート作成など、緻密で繊細な作業が多く、一つの案件にかかる工数は非常に大きくなります。
また、顧客や上司からのフィードバックにより、再調査や再分析が必要になるケースも珍しくありません。調査結果が予想外の方向に進んだ場合は、内容を根本から見直すこともあり、仕事に終わりが見えにくいという声も聞かれます。
締切が迫ると徹夜で対応するスタッフもおり、体力だけでなく精神的なタフさも求められる職場環境です。
勤務時間外も連絡・対応が求められることがある
プロジェクトによっては、納期直前の修正や顧客対応が発生し、勤務時間外に連絡が入るケースもあります。
特にコンサル型シンクタンクでは顧客とのやり取りが頻繁で、夜間や休日に急ぎの確認や資料の差し替え対応が求められることも珍しくありません。
さらに、チームメンバーが海外にいる場合、時差に配慮したミーティングが早朝や深夜に設定されることもあります。そのため、仕事とプライベートの境界があいまいになり、オンとオフの切り替えが難しいと感じる人も多くいます。
ワークライフバランスを重視する方にとっては、負担に感じる場面があるかもしれません。
国内企業が少なく業務負担が重くなりがち
日本国内のシンクタンクは外資系と比べて数が少なく、1人あたりの業務負担が重くなる傾向があります。特に中小規模のシンクタンクでは、調査・分析から報告書作成、プレゼン、顧客対応までを一人で幅広く担当することも多いです。
そのため、明確な役割分担がない中でマルチタスクが求められるケースも珍しくありません。
さらに、社会的責任や外部からの期待も大きく、そうしたプレッシャーの中で長期間働き続けると、心身ともに疲弊しやすくなります。その結果、若手のうちに燃え尽きてしまう人もおり、激務とされる要因の一つとなっています。
シンクタンクが向いている人

シンクタンクは、調査・分析・提言を通じて社会や企業の意思決定を支援する知的専門職です。ここでは、シンクタンクに向いている人の特徴を詳しく紹介します。
情報収集や分析が好きな人
シンクタンクの主な業務は、膨大なデータや文献をもとに課題の本質を見極めることです。そのため、日常的に情報収集が好きで、新しい知識に対する好奇心を持ち続けられる人には、高い適性があります。
特に、断片的な情報から全体像を導いたり、複数の資料を比較して矛盾点を見つけ出すような分析力が求められます。
加えて、信頼性のある情報を見極めるリテラシーも欠かせません。ただ調べるだけでなく、それを精度の高いアウトプットに結びつける姿勢が重要です。
日々変化する経済や社会の動きをキャッチアップし、自分なりに仮説を立てて検証するプロセスを楽しめる人にとって、非常にやりがいのある職種と言えるでしょう。
論理的に物事を捉えられる人
シンクタンクの業務では、複雑な課題を整理し、クライアントや社会に対して納得感のある説明を行う力が求められます。そのため、論理的思考力は欠かせないスキルです。
与えられた問題に対して、どの要素が影響しているのかを分解し、原因と結果を筋道立てて考えられる人はシンクタンクでの活躍が期待されます。また、資料作成やプレゼンにおいても、数字や根拠に基づいた論理的な構成力が必要です。
感情や直感ではなく、冷静かつ客観的に物事を分析・判断できるタイプの人は、顧客からの信頼を得やすく実務でも高く評価される傾向にあります。
知識を深めて新たな発見につなげられる人
シンクタンクの仕事は、単に情報を調べるだけでは完結しません。既存のデータや知見をもとに、自分なりの視点や価値を創出することが求められます。
つまり、知識を受け取るだけでなく、咀嚼・構造化し、そこから新たなアイデアを導き出す力が重要です。専門分野の知識を深める姿勢はもちろん、異なる分野を結びつけて新しい切り口を見出せる柔軟性も評価されます。
未知のテーマにも前向きに取り組み、深掘りすることを楽しめる人は、シンクタンクの業務に自然と馴染むでしょう。学びを成果へとつなげる姿勢が求められる職場です。
周囲と良好な関係を築ける人
シンクタンクではチームで進めるプロジェクトが多く、1人で完結する業務は限られています。そのため、周囲と良好な関係を築きながら協力して成果を出せる人に向いています。
特に、クライアントとの信頼構築や、上司・同僚と調査方針をすり合わせる場面では、丁寧で的確なコミュニケーション力が欠かせません。相手の意図を正確に読み取り、ロジカルかつ穏やかに自分の意見を伝えるスキルも求められます。
また、地道な作業が続く中でも、周囲と協力しながらチームの士気を保てる柔軟性と忍耐力も重要です。高度な分析力に加えて優れたコミュニケーション力を持つ人は、シンクタンクで長く活躍できる素質があると言えるでしょう。
シンクタンクが向いていない人
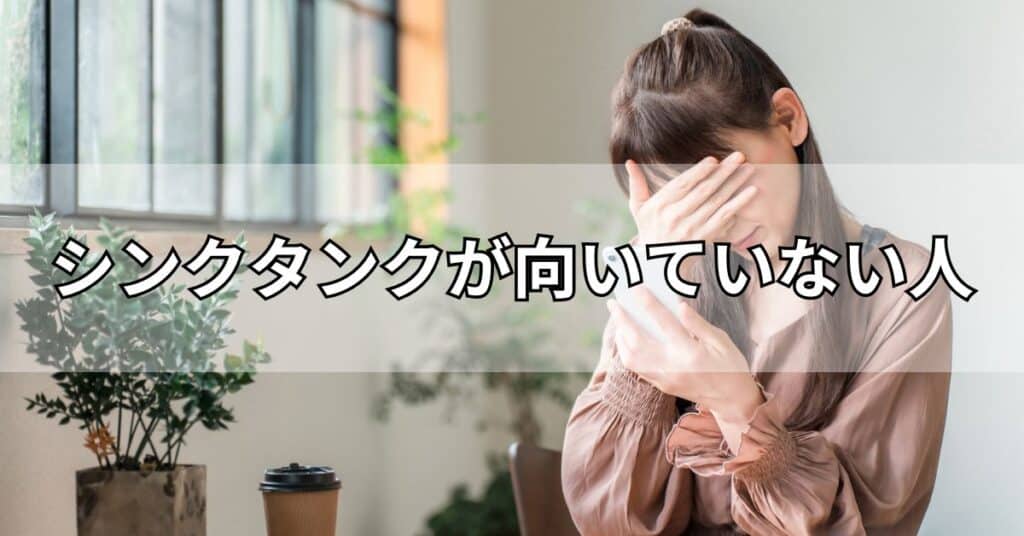
いくら優れた知識を持っていても、業務や人間関係の特性とマッチしない場合には、ストレスを感じやすく長続きしないこともあります。ここでは、シンクタンクの仕事に向いていない人の特徴を具体的に解説します。
人との関わりが得意ではない人
シンクタンクと聞くと、一人で黙々とリサーチを進める仕事をイメージしがちですが、実際には社内外の関係者とのやり取りが非常に多い職場です。
社内ではチームでの共同プロジェクトが一般的で、プロジェクトマネージャーやアナリスト、クライアント担当など複数の役割が連携しながら成果を出していきます。
また、クライアントと密にコミュニケーションを取りながら課題を深掘りしたり、報告書へのフィードバックを受けたりする機会も多いため、対話力や信頼関係を築く力が欠かせません。
人との関わりをできるだけ避けたい、できれば一人で完結する仕事がしたいと考えている方にとっては、こうした環境がストレスとなりやすく、あまり向いているとは言えないでしょう。
自己主張が強く意見を曲げにくい人
シンクタンクでは、論理的な議論を重ねて最適な結論に導くことが求められるため、チーム内での意見交換や立場の異なるメンバーとの協働は日常的に行われます。
この際、自分の意見に固執しすぎたり、他人の視点を受け入れる柔軟性が欠けたりしていると、議論が滞り、衝突や孤立を招く原因になるでしょう。
相手のロジックを理解し、建設的に議論を進める力が重視される職場であるため、自分の正しさばかりを主張するタイプの人はチーム内で信頼を得るのが難しくなります。主張すべきときと譲るときの判断力やバランス感覚が求められる仕事です。
新しい挑戦を避けがちな人
シンクタンクの仕事では、社会の動向やクライアントの課題に応じて、常に新しいテーマや未知の分野に取り組む姿勢が求められます。特に、社会課題が複雑化する現代においては、過去の事例や既存の枠組みだけに頼る提言では不十分です。
そのため、新たな知識や手法を学ぶ意欲が乏しかったり、変化を好まず現状維持にこだわったりする人は、シンクタンクのスピード感や求められる水準に適応するのが難しくなるでしょう。
また、研究対象の急な変更や担当分野の追加など、環境の変化も日常的に発生するため、柔軟な対応力が欠かせません。新しい挑戦を前向きに楽しめない人にとっては、成長を実感しにくく、いずれ限界を感じてしまう可能性があります。
シンクタンクでの継続的なキャリア形成のコツ
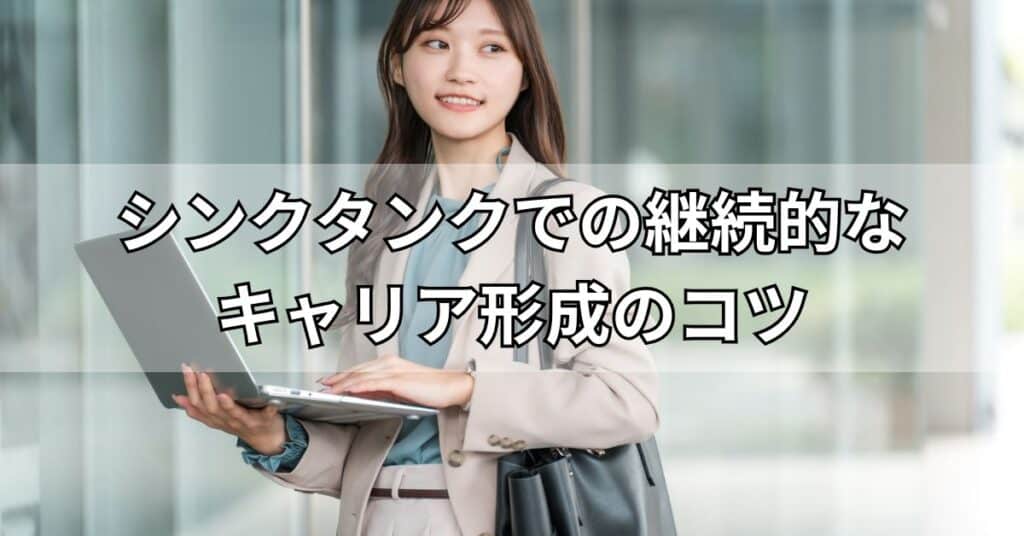
シンクタンクで長く活躍するためには、専門知識やスキルの習得だけでなく、自分に合った環境を選び、キャリアビジョンを明確に持つことが重要です。ここでは、シンクタンクで自分らしくキャリアを築くための具体的なコツをご紹介します。
定着率の高い企業を見極める
シンクタンク業界は激務になりやすく、離職率が高い企業も少なくありません。そのため、長く働ける環境かどうかを判断するうえで、定着率の高さは重要な指標となります。
定着率の高い企業は業務量のバランスが取れていたり、教育体制が整っていたりと、風通しの良い社風を持っている傾向があります。企業研究の際には、平均勤続年数や離職率、社員の口コミなどを確認することが大切です。
また、採用面接では育成体制の内容や、入社後のキャリアパスの例などを逆質問することで、企業が社員の成長をどう支えているかを見極められます。短期離職が多い企業では精神的な負担も大きくなりやすいため、定着率の高い職場を選ぶことが重要です。
自分の強みと価値観を見つめ直す
シンクタンクでは多様な調査・分析業務を行う中で幅広い知識が求められる一方、自分の専門性や個性を活かせる場面も多くあります。だからこそ、自分の強みや価値観をしっかりと理解し、それを活かせる業務に集中することが、継続的な成長につながる重要なステップです。
たとえば、数字に強い人は経済・金融分野、政策に関心のある人は公共政策分野など、自分が最も力を発揮できる領域を明確にしておくと良いでしょう。
また、何を重視して働きたいのかといった価値観を整理しておくことで、企業選びや異動希望の際にも役立ちます。自己理解を深めることでモチベーションを維持しやすくなり、ぶれないキャリア戦略を描くことが可能です。
将来のビジョンを明確にする
シンクタンクで長期的なキャリアを築くためには、将来どのような専門家・人材になりたいのかをできるだけ具体的に描いておくことが重要です。
たとえば、「10年後に独立系の研究者として活躍したい」「公共政策に深く関与できるポジションを目指したい」など、自分の価値観や関心と結びつけて将来像を明確にすることで、進むべき方向が見えやすくなります。
また、そのビジョンに近づくために必要な経験やスキル、資格、異動希望などを整理し、上司や人事と定期的にキャリア面談を行うのも効果的です。明確な目標を持って行動することで、日々の業務に意味を見出しやすくなり、離職リスクの低減にもつながります。
シンクタンク転職におすすめのエージェント
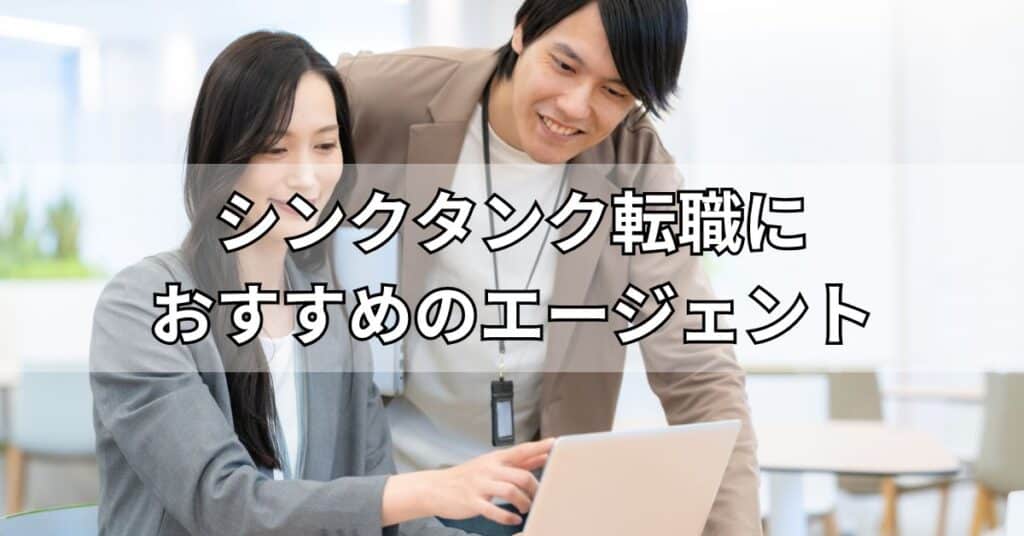
シンクタンクへの転職は求められるスキルや知識の幅が広く、業界特有の情報も必要とされるため、転職エージェントの活用が欠かせません。ここでは、シンクタンク転職におすすめのエージェントを紹介します。
MyVision
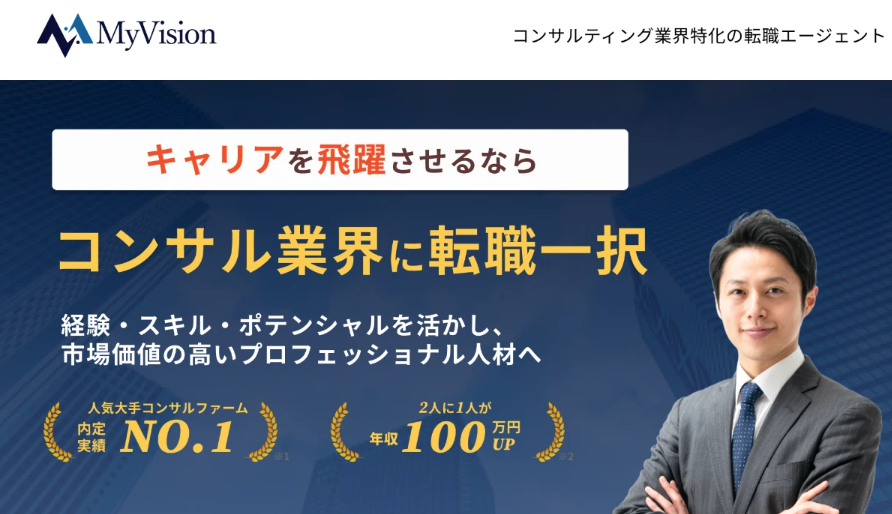
- コンサル特化の転職支援
- 支援実績1,000名以上
- トップ戦略ファーム出身者が提供するサービス
MyVisionはコンサル特化の転職支援で、理想のキャリアアップを目指せる転職エージェントサービスです。Japan Business Research 転職エージェント部門 6項目で高評価を獲得※するなど、多くの実績を持ちます。
「コンサル業界での実務経験者」や「同業界の転職支援で豊富な実績を持つプロ」が在籍しており、質の高いサポートを受けられるのが大きな特徴です。
200社以上のコンサルファームと強いネットワークを築いており、国内ほぼすべての主要ファームへの紹介が可能です。また、過去の支援実績に基づいた独自の選考対策も提供しており、実践力を磨ける点も魅力です。
さらに、元コンサルタントと本番さながらの模擬面接を繰り返し行えるなど、手厚いサポート体制もMyVisionならではの強みです。
| MyVisionの基本情報 | |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社MyVision(マイビジョン) |
| 公式サイト | https://my-vision.co.jp/ |
| 公開求人数 | 非公開(2025年7月14日現在) |
| 主な求人職種 | コンサル、金融業界 |
関連記事>>MyVision(マイビジョン)の評判・口コミ
アクシスコンサルティング

- コンサル・ポストコンサルの採用・転職支援サービス
- 数百名のCxOの転職を支援
- 中長期のキャリアサポート
アクシスコンサルティングはコンサル業界専門の転職支援に特化し、これまでに1万人以上のキャリア支援実績を持つエージェントです。
シンクタンクや総合系ファーム、事業会社の経営企画職など、ハイレベルな職種への転職に強みを発揮しています。最大の特徴は、業界に精通したコンサルタントが多数在籍している点です。
各ファームやシンクタンクの内情にも詳しく、「どの企業がどんな人材を求めているか」「選考で重視されるポイントは何か」といった実践的な情報を提供してくれます。
さらに、短期的な転職だけでなく、長期的なキャリア形成を見据えたサポートにも力を入れています。今すぐ転職を考えていない方への中長期支援やフリーランス向けの案件紹介も行っているので、ぜひ興味がある方は登録しましょう。
| アクシスコンサルティングの基本情報 | |
|---|---|
| 運営会社 | アクシスコンサルティング株式会社 |
| 公式サイト | https://axc-g.co.jp/ |
| 公開求人数 | 非公開(2025年7月14日現在) |
| 主な求人職種 | IT、金融、コンサル業界ほか |
関連記事>>アクシスコンサルティングの評判・口コミ
コンコードエグゼクティブグループ

- 未来を作るリーダーを支援
- 内定を勝ち取る選考対策を実施
- 信託された特別紹介ルートを持つ
コンコードエグゼクティブグループは、ハイクラス層向けの転職支援に特化したエージェントで、戦略系コンサルファームや大手シンクタンクへの転職成功実績が豊富です。
年収1,000万円以上のポジションを多数取り扱っており、経営幹部候補やエリート層のキャリア支援に強みを持ちます。最大の特徴は求職者一人ひとりの「人生観」や「ビジョン」に寄り添ったキャリア設計を行ってくれる点です。
単なる求人紹介にとどまらず、5年後・10年後のゴールを見据えた中長期的な提案が受けられるため、明確なキャリア志向を持つ方にとって理想的なパートナーと言えるでしょう。
また、特別案件や特急選考といった限定紹介も充実しています。幹部ポジションやチーム採用、さらには経営幹部との面談から始まる選考など、通常では得られない機会も多数ある点は大きな魅力です。
| コンコードエグゼクティブグループの基本情報 | |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社コンコードエグゼクティブグループ |
| 公式サイト | https://www.concord-group.co.jp/ |
| 公開求人数 | 非公開(2025年6月8日現在) |
| 主な求人職種 | IT、金融、コンサル業界ほか |
関連記事>>コンコードエグゼクティブグループの評判・口コミ
シンクタンクの激務に関する疑問

最後に、シンクタンクの激務に関する疑問に丁寧にお答えします。転職を検討する前に、自分に合っている職場かどうかを見極める材料としてご活用ください。
シンクタンクへの転職は難易度が高いですか?
シンクタンクへの転職は、比較的難易度が高いとされています。特に研究職やアナリスト職では、業界経験や専門知識、大学院修了といった学歴が求められることも多く、書類選考の段階で不採用となるケースも珍しくありません。
ただし、近年は職種の多様化が進んでおり、調査補助やリサーチサポートなど、未経験からでも挑戦しやすいポジションも増えています。
異業種からの転職を目指す場合は、論理的思考力や分析力、リサーチスキルなどを具体的な実績とともにアピールすることが重要です。特に、IT・経済・公共政策などの分野にバックグラウンドがある人は、歓迎される傾向があります。
シンクタンク業界のワークライフバランスは?
シンクタンク業界のワークライフバランスは、企業によって大きく異なります。一部では長時間労働や納期前の残業が常態化している職場もありますが、業界全体としては改善傾向にあるようです。
近年では、政府系シンクタンクや民間企業でもホワイト企業化が進み、フレックスタイム制度や在宅勤務を導入する例が増えています。また、プロジェクト単位で業務が進むため、スケジュール管理さえできていれば、柔軟な働き方も可能です。
ただし、繁忙期や急な資料作成、政策提言への対応に追われることもあるため、精神的なタフさは求められます。働き方改革の影響を受け、徐々に労働環境が整いつつある業界です。
シンクタンクにはホワイト企業もありますか?
激務のイメージが強いシンクタンク業界ですが、実際にはホワイト企業も存在します。たとえば、野村総合研究所(NRI)は業界トップクラスの待遇と人事制度を備えており、ワークライフバランスの面でも高い評価を受けています。
また、日本総合研究所は育児休暇の取得率が高く、働きやすい職場として定評があります。さらに、三菱総合研究所(MRI)ではフレックス制度や充実した福利厚生が整っており、社員の定着率も良好です。
これらの企業は、激務というシンクタンク業界のイメージを覆す代表例です。企業選びの際は、口コミサイトや社員の声、各種制度の有無などを参考にすることで、働きやすい職場を見極めやすくなります。
シンクタンクで働くにはどのような学歴が必要ですか?
シンクタンクの職種によって求められる学歴は異なりますが、研究職やアナリスト職を目指す場合は大学卒業以上、特に修士・博士課程を修了していると有利とされています。
経済学や政治学、社会学、統計学、情報学など専門性の高い分野が多く、大学院での研究経験が評価される傾向があります。一方で、実務職や調査補助スタッフ、事務系ポジションでは、学歴よりも実務経験やスキルが重視されます。
そのため、必ずしも高学歴が必須というわけではありません。職種ごとの応募要件をしっかり確認し、自分の強みを活かせるポジションを選ぶことが大切です。
文系出身でもシンクタンクで働けますか?
文系出身者でも、シンクタンクで活躍することは十分可能です。実際に多くの文系人材が、政策調査や社会調査、経済分析、コンサルティングなどの分野で力を発揮しています。
中でも、論理的思考力や文章作成力、資料作成スキル、プレゼンテーション力といった文系出身者が持ちやすい強みは、シンクタンクの業務で評価されるでしょう。
さらに、公共政策や地域経済、教育、福祉などのテーマに関心がある人は、文系の知見を活かせるフィールドが多く用意されています。加えて、統計ソフトやExcel、PowerPointなどのツール操作ができれば、実務面での即戦力にもなります。
シンクタンクの「研究員」とはどのような職種ですか?
シンクタンクの研究員は、調査や分析を通じてクライアントや社会の課題解決に貢献する職種です。仕事内容は文献調査やデータ分析、インタビュー調査、レポート作成、提言資料の作成など多岐にわたります。
政府・自治体・企業などから依頼されたテーマに対して、調査結果をもとに政策提言や戦略の提案を行うことが多く、高い専門性と成果が求められます。
また、研究員には、分野ごとの専門知識に加え、統計分析スキル、プレゼンテーション力、コミュニケーション力も不可欠です。プロジェクト単位で複数の業務を並行して進める場面も多いため、スケジュール管理力やストレス耐性も求められます。
シンクタンクの激務は実情を見極めて転職成功しよう
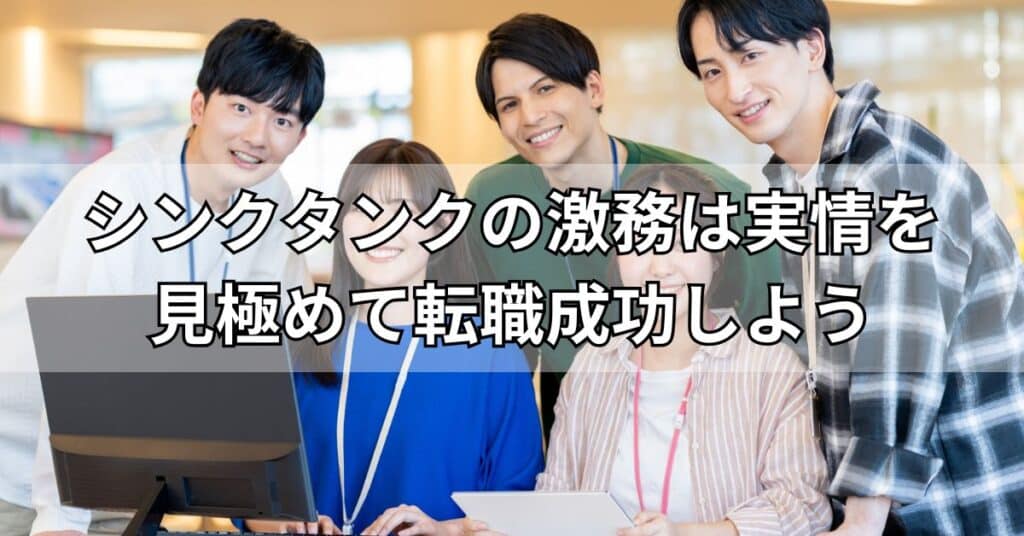
シンクタンクは高度な分析力や論理的思考が求められる分、やりがいの大きい仕事ですが、激務と感じる人も少なくありません。特に、成果主義の風土やタイトな納期、長時間労働などがシンクタンクが激務の理由として挙げられることがあります。
しかし、自分に向いているかを見極めたうえで、働き方やキャリア形成の視点を持てば、継続的に活躍することも十分可能です。ホワイトな職場環境を整えている企業も存在するため、転職を検討する際は、自分の強みや価値観に合った企業を慎重に選ぶことが大切です。