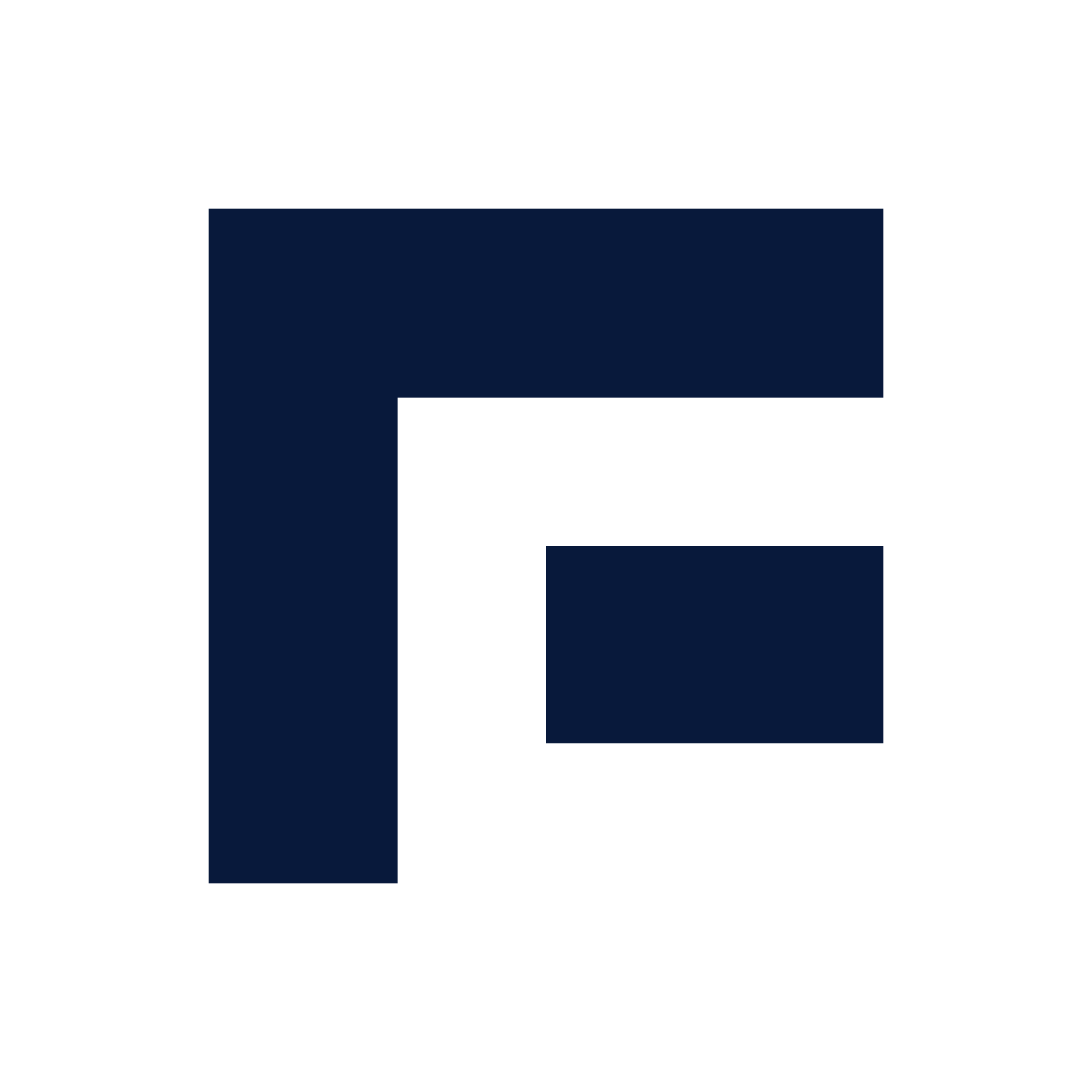少子高齢化が進む日本において、医療機器の進化と普及は、国民の健康や医療体制の持続可能性に大きく関わるテーマとなっています。
しかし、その実現には数多くのハードルが存在します。規制対応や開発資金の確保、ビジネスモデルの構築など、医療機器開発には多面的な困難が伴います。特に、これまで医療機器に関わってこなかったスタートアップや異業種からの参入企業にとっては、制度の複雑さ自体が大きな障壁になり得ます。
そうしたなか、「経済的かつ効率的で最適なロードマップでの承認獲得」を掲げ、実用化支援に取り組むのが東北大学ナレッジキャスト株式会社です。
今回は、医薬品医療機器総合機構(PMDA)で12年にわたり審査・相談業務に携わり、現在は同社のシニアコンサルタントとして活躍する鈴木 友人さんに、支援の哲学と日本の医療機器開発の未来についてお話を伺いました。

東北大学ナレッジキャスト株式会社
鈴木 友人様
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)に12年在職し、主に心臓血管系の医療機器を中心に承認審査及び相談業務に従事。PMDA在職中に東京大学医学部附属病院及び日本医療研究開発機構(AMED)に出向し、医療機器等の研究開発支援や予算事業の管理運営を担当。
規制と現場、両方を知る“実装志向”の支援
──(コンサルGO編集部)まずは鈴木さんのご経歴について教えてください。
鈴木:共立薬科大学大学院で博士号(薬学)を取得後、医薬品医療機器総合機構(PMDA)の医療機器審査部で審査専門員として循環器系医療機器の承認審査や相談業務に従事していました。
PMDAに6年間勤務後、東京大学医学部附属病院に出向し、医療機器開発を含む医療系シーズに関するコンサルティングや研究開発支援に携わりました。
その後はPMDA医療機器審査部で再度の勤務を経て、日本医療研究開発機構(AMED)に出向して医療機器の研究開発に関する予算事業の管理や運営を担当し、日本の医療機器開発推進に尽力してきました。
これらの経験を経て、2020年からは東北大学ナレッジキャスト株式会社の医療機器等開発支援グループで、グループマネージャー兼シニアコンサルタントとして活動しています。現在は、医療機器の実用化を目指す企業へのコンサルティングや、資料作成支援などを幅広く担当しています。
PMDA出身者がサポート!医療機器の開発を包括的に支援するプロフェッショナル集団
──PMDAや大学、研究機関など多様な現場を経験されたことが、御社での活動にも活かされているのですね。現在の事業内容についてもご紹介ください。
鈴木:当社は、国立大学法人東北大学が100%出資して設立された会社であり、大学の研究成果や知的資産を活用して産学連携事業を展開しています。事業の柱は大きく2つあり、ひとつは研修・講習事業、もうひとつが医療機器開発支援に特化したコンサルティング事業です。
コンサルティング事業では、開発戦略の立案から承認申請資料の作成支援まで、製品の実用化に向けた包括的なサポートを行っています。PMDA出身者など実務経験を有する専門人材が在籍しており、薬事対応を含めた専門性の高い支援が可能です。
PMDA提出用資料の作成支援をはじめ、非臨床試験、治験、承認申請といった各フェーズでのアドバイスを行っており、あらゆる疾患領域や前例のない新規医療機器への対応も得意としています。
また、個別相談会やセミナー、企業研修などを通じた人材育成・体制強化にも力を入れています。
経済的かつ効率的に進めるための「最適なロードマップ」で承認を目指す
──支援範囲の広さと専門性の高さが印象的です。支援において、特に大切にされている方針はありますか?
鈴木:私たちが重視しているのは、お客様が医療機器の承認を「最短かつ最小の工数」で獲得できるよう支援することです。不要な作業を省き、コストパフォーマンスとタイムパフォーマンスを最大限に高めることで、お客様の負担をできる限り軽減した効率的な支援を提供しています。
これは、単に合格最低限を目指すのではなく、お客様の事業を経済的かつ効率的に進めるための最適なロードマップを提示することを意識しています。
スタートアップから異業種まで。誰もが頼れる支援体制
──どのような企業や業種を対象にされているのでしょうか?
鈴木:当社は、医療機器を開発したいと考えるすべての方々を対象としており、特に業界の制限は設けておりません 。
既存の医療機器開発・販売企業はもちろん、新規参入を目指すスタートアップ企業や異業種からの参入者、さらにはアカデミアからの起業家まで、幅広く支援しています 。
支援フェーズとしては、開発アイデア段階から最終的な承認まで、基本的にすべてのフェーズに対応しており、お客様のニーズに合わせた柔軟なサポートを提供しています 。
ビジネス成立を前提に“保険戦略”から着手
──業界・フェーズを問わず、あらゆる開発者の挑戦に応えているのですね。そうした中で、御社ならではの進め方にはどのような特徴がありますか?
鈴木:はい。特徴的な進め方として、新しい医療機器の場合、薬事戦略よりも先に「保険に関する相談」を行うというアプローチをとっています。
開発しても保険収載されなければビジネスとして成立しません。そこで、まず厚生労働省に保険収載に関する要件や必要データを確認し、その上で薬事戦略を立案します。この手順を踏むことで、開発の全体像と現実的なアクションプランを早期に把握でき、効率的な開発ロードマップを描くことが可能になります。
臨床試験を回避し、時間と費用を大幅削減した成功事例
──ビジネス成立を前提としたアプローチですね。印象に残っている支援事例はありますか?
鈴木:代表的な事例として、当初臨床試験が必要とされていた案件に対し、文献評価などの効率的な戦略を提案し、臨床試験の実施を不要にしたケースがあります 。
文献を精査し、臨床評価報告書としてまとめた上でPMDAと協議を行った結果、臨床試験なしでの承認取得に成功しました。このことで、お客様は数億円規模の臨床試験費用と1年以上の開発期間を削減することができました。
行政との橋渡しを担う「翻訳者」としての役割
──まさに実務的で経済的なインパクトの大きい支援ですね。そうした支援に対して、企業側からはどのような評価を得ていますか?
鈴木:支援先企業からは、主に規制当局とのコミュニケーションにおける橋渡し役としての能力を高く評価いただいています 。当社が介入する前は難航していた案件でも、行政サイドの意図を正確に理解し、お客様の意図を当局に分かりやすく伝えることで、円滑な意思疎通を可能にしました 。
特に、行政サイドの言葉を「翻訳」し、お客様が抱える疑問や不安を解消することで、妥当な要求形成と解決の道筋が見えたというフィードバックを多くいただいております 。
元規制従事者だからこそ描ける最適なロードマップ
──その「翻訳力」は、まさに実務経験に裏打ちされたものですね。あらためて、御社ならではの強みについて教えてください。
鈴木:当社の最大の強みは、行政での実務経験者がコンサルテーションをしているという点にあります 。これにより、行政と企業双方のロジックや思考パターンを深く理解し、相手が納得しやすい提案が可能です 。
例えるなら「元ハッカーによるサイバーセキュリティ対策」のように、規制側の視点と企業側の視点の両方を知っているからこそ、最短かつ最も経済的な承認への道筋を示し、日本の医療機器エコシステムの発展に貢献できると考えています 。
医療機器エコシステムを日本に根づかせたい
──この知見を、今後どのようなテーマに活かしていくお考えですか?
鈴木:日本の医療機器産業は輸入超過であり、国内から質の高い医療機器がもっと生まれる土壌があるにもかかわらず、そのエコシステムが十分に成熟していません 。
元行政従事者としての経験も活かし、困難な課題を抱える新規チャレンジャーを支援することで、日本の医療機器開発のエコシステム構築の一助となることを目指しています 。
そういった意味でも今後は日本から世界に通用する医療機器を生み出すことに注力していきたいと考えています 。特に、新たな医療機器開発に挑戦するスタートアップ企業や異業種からの新規参入企業への支援を強化したいと考えています 。
一方で、日本の患者さんの事を考えると、海外で開発された優れた医療機器を、いち早く国内で使えるようにすることも重要ですので、海外製医療機器の国内導入に関しても、支援を強化していきたいと考えています。
医療機器開発に挑むすべての企業へ
──最後に、この記事を読んでいる企業の方々へメッセージをお願いします。
鈴木:医療機器業界にはまだ成功事例が多くありませんし、支援人材も限られているのが実情です。私たちは、異業種からの参入企業、アカデミア発の革新的な技術を持つスタートアップなど、挑戦を続けるすべての方々を全力でサポートしたいと考えています。
また、海外製品の日本導入に関する支援も積極的に行っています。制度や戦略にお悩みの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
──ありがとうございました。医療機器の新規開発や日本市場への導入を検討中の方は東北大学ナレッジキャスト株式会社までお問い合わせください。