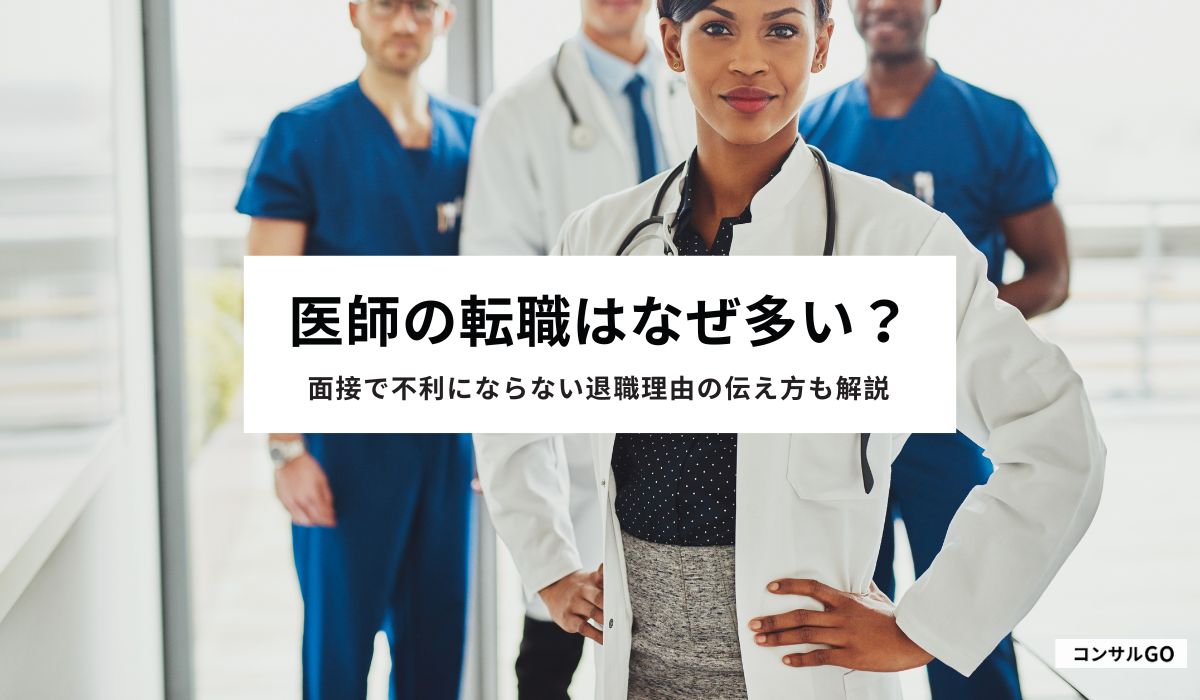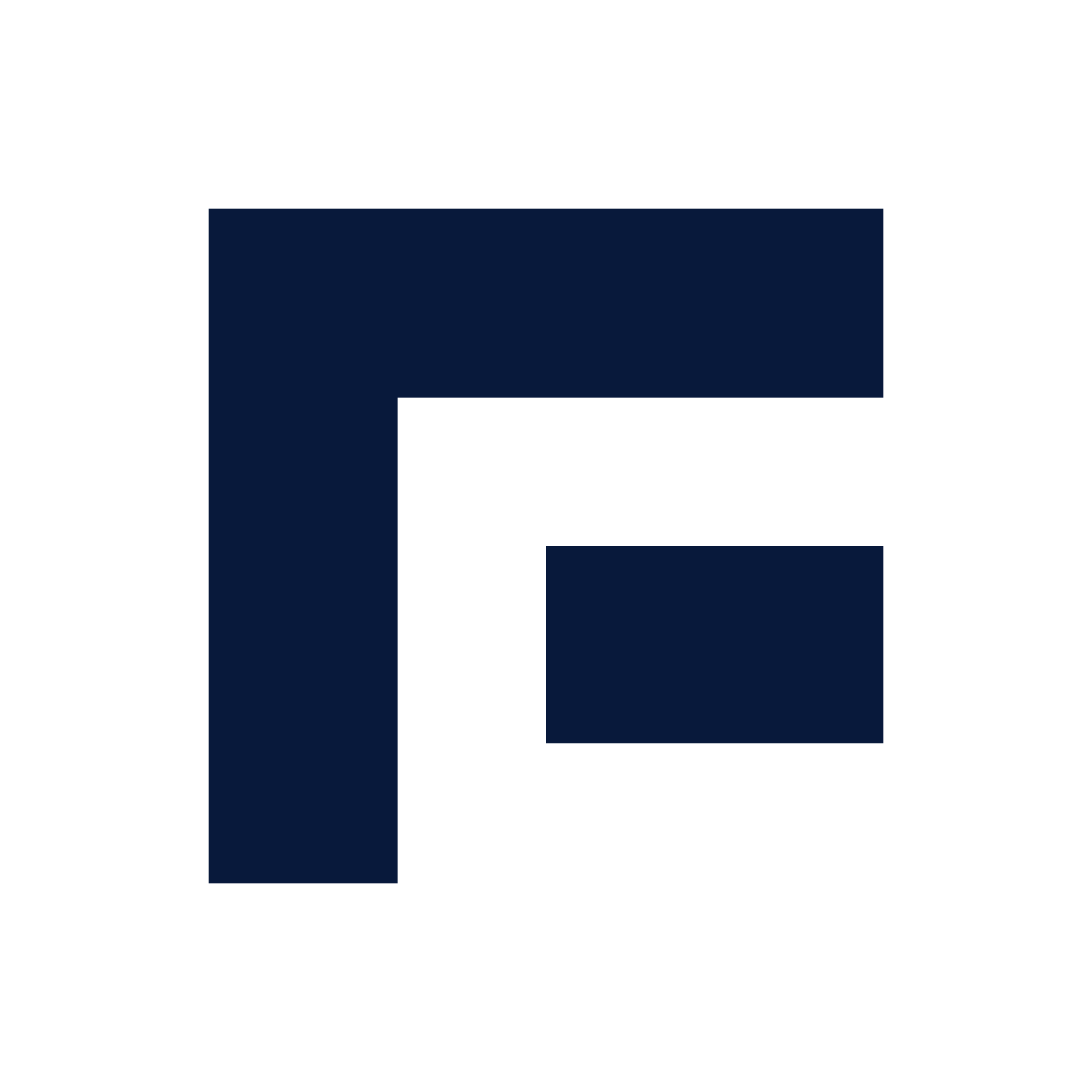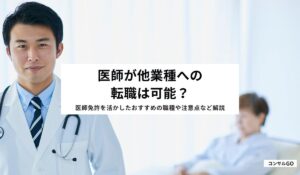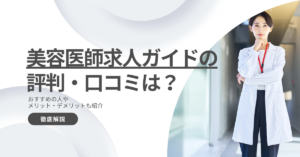「医師は転職が多い」と感じる方も多いでしょう。実際、過酷な労働環境や人間関係、将来への不安などを背景に、多くの医師が転職を経験しています。
その一方で、「転職回数が多いと面接で不利になるのでは」と不安を抱く方も少なくありません。この記事では、医師の転職回数に関する実態や、転職を成功に導くためのポイントを解説します。
読み進めることで、自分の転職理由に自信を持ち、次の職場選びに前向きになれるヒントが得られるはずです。ぜひ参考にしてみてください。
医師におすすめの転職エージェント3選
| サービス名 | 特徴 |
|---|---|
 医師転職ドットコム 医師転職ドットコム | 7万件以上の紹介成約実績!利用者の6割以上が年収アップを実現 医師専任コンサルタントの交渉により給与から勤務条件まで細かな希望が叶う。丁寧でスピーディな対応も好評 |
 民間医局 | 20年以上の実績!契約医療機関18000件以上!医師向け総合サービス 医師の転職支援や求人紹介、医師向けの保険・情報提供サービスから開業支援や継承・閉院のサポート、コンサルティングなど、幅広いサービスが魅力 |
 Dr.転職なび | 利用した医師の総合満足度97% 専任のエージェントは全員医療経営士資格を保有。医療業界に精通した担当者が選んだ求人を提案可能。プライバシーマークを取得しており、今の勤務先に転職活動を知られる心配がない。 |
関連記事>>医師転職エージェントおすすめ
医師の多くが一度は転職を経験している
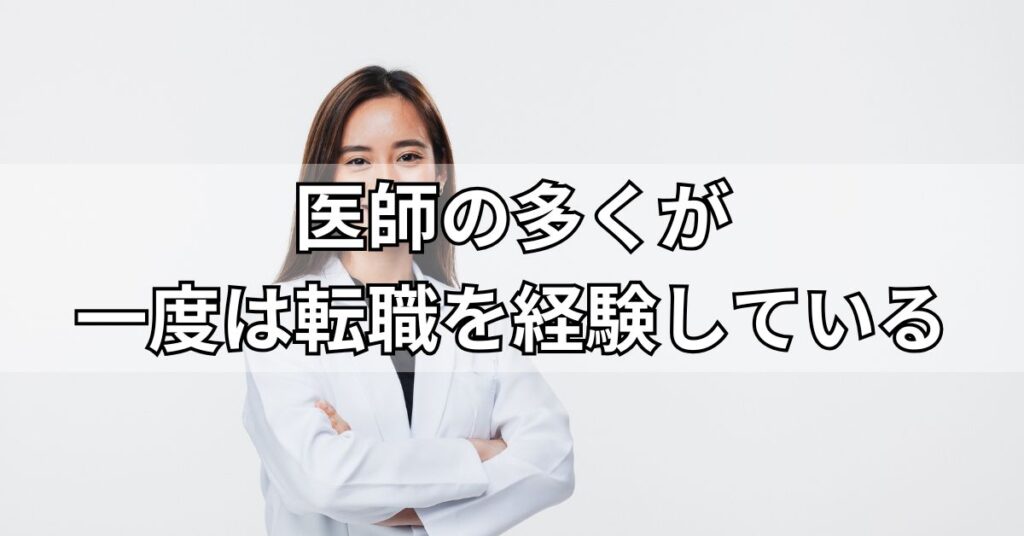
医師の転職は珍しいことではありません。ここでは、大学病院と民間病院・診療所での医師の転職回数について詳しくみていきましょう。
大学病院のケース
大学病院勤務の医師は、一般的に転職回数が少ない傾向にあります。大学病院のような大規模医療機関では、専門性を高めたり研究に専念したりする機会が多く、長期的な勤務が前提となることが多いためです。
さらに、医局内での人事異動が定期的にあるため、人間関係に課題があっても異動によって環境が変わることが期待でき、離職にまで至らないケースもあるでしょう。
加えて、安定した雇用条件や充実した研究環境、学会活動への参加機会といったメリットも、転職を控える要因の一つです。ただし、ライフスタイルの変化や将来のキャリア形成を目的に、あえて転職を選ぶ医師も存在します。
民間病院・診療所のケース
民間病院や診療所で働く医師は、比較的転職回数が多い傾向にあります。これらの職場では、研修中に多様な症例や業務に触れる機会があり、その過程で自身の適性やキャリア目標が明確になることが少なくありません。
その結果、現在の職場とのミスマッチを感じ、転職を選択する医師も多くあるでしょう。転職回数が3〜5回以上になるケースも珍しくなく、複数の職場を経験することで理想のキャリアを築こうとする医師も少なくありません。
近年では、美容クリニックや産業医、フリーランスといった新たな働き方が広がりつつあり、それに伴い医師の転職回数は今後も増加傾向が続くと考えられます。
医師が辛い・やめたいと思うのはなぜ?主な転職理由
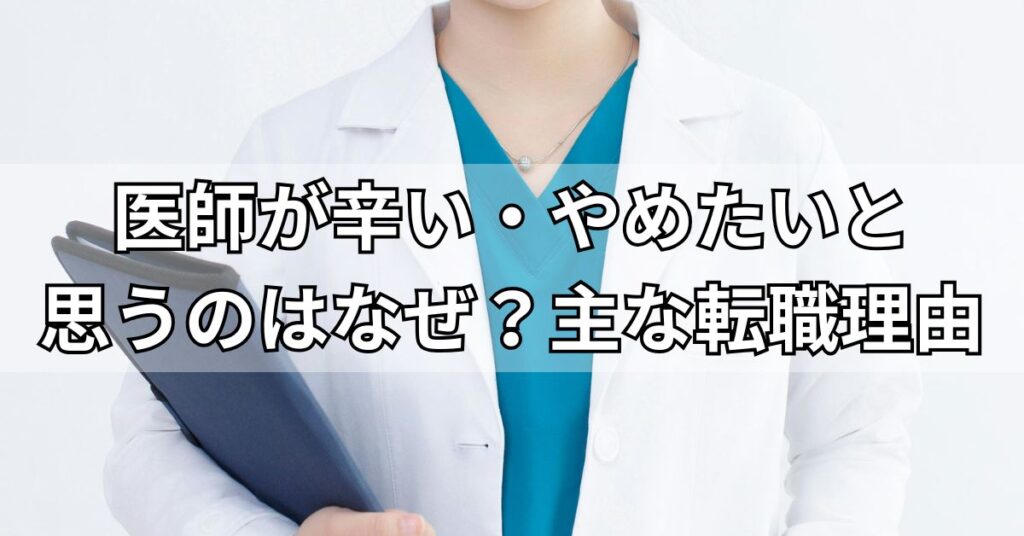
医師が転職を考える背景には、辛さや辞めたいと感じる要因が複数あります。
過酷な業務により心身ともに消耗してしまった
医師が「辛い」「やめたい」と感じる主な転職理由の一つに、過酷な業務による心身の消耗があります。医師という職業は長時間労働や不規則な勤務が常態化しやすく、さらに患者の命を預かる責任の重さから、常に緊張状態が続きやすい仕事です。
その結果、プライベートの時間が確保できず、燃え尽き症候群や体調不良に陥り、転職を検討する医師も少なくありません。
近年では、医師の勤務時間の短縮やシフト制度の導入など働き方改革が進んでいます。心身のバランスを保ちながら働ける職場を探すことも、現実的で前向きな選択肢となりつつあります。
将来を見据えて収入を見直したい
医師が「辛い」と感じて転職を考える理由の一つに、将来を見据えた収入の見直しがあります。医師の収入は、勤務先の種類や規模、地域によって大きく異なり、格差が生じやすいのが現実です。
また、診療科によっても収入の傾向が異なります。たとえば、外科系は手術による報酬が見込めるのに対し、内科系は外来患者数に左右されやすく、経済的な安定性に差が出ることも。
さらに、一般病院と診療所とでは平均年収に数百万円の差が生まれるケースもあります。こうした中で、今後の生活や将来設計を見据え、より高い報酬や安定を求めて転職を検討する医師が増えています。
他院・他科での経験を通じて専門性を高めたい
現在の職場では得られない専門性の習得や先進的な医療技術の習得を目指し、転職を希望する医師も少なくありません。
医師としてキャリアを積むなかで、特定分野の専門医資格を取得したい、より高度な症例に携わりたいと考えたとき、今の職場がその環境を提供できない場合があります。
たとえば、地域の一般病院で内科医として勤務していると、専門性の高い症例に触れる機会が限られます。スキルアップの面では、物足りなさを感じることもあるでしょう。
こうした場合、キャリアアップを見据えて環境を変えることは、専門医としての成長を実現するうえで現実的かつ前向きな選択肢といえるでしょう。
ライフステージの変化に伴う転職
医師が転職を考える理由のひとつに、ライフステージの変化に伴う生活や仕事環境の変化があります。特に女性医師の場合、出産や育児を機に勤務形態の見直しが必要となるケースが多いです。
これまでフルタイムで働いていた医師が、育児を優先して非常勤勤務やフリーランスへの転向を選ぶケースも珍しくありません。近年では託児施設を併設する医療機関や、時短勤務に対応した職場も増えており、子育てと仕事を両立しやすい環境が整いつつあります。
柔軟な働き方を提供する職場を選ぶことで、ライフスタイルの変化に応じた働き方が可能となり、より充実したキャリアと家庭生活の両立が実現できるでしょう。
医師の転職回数が多いと起こりうるデメリット
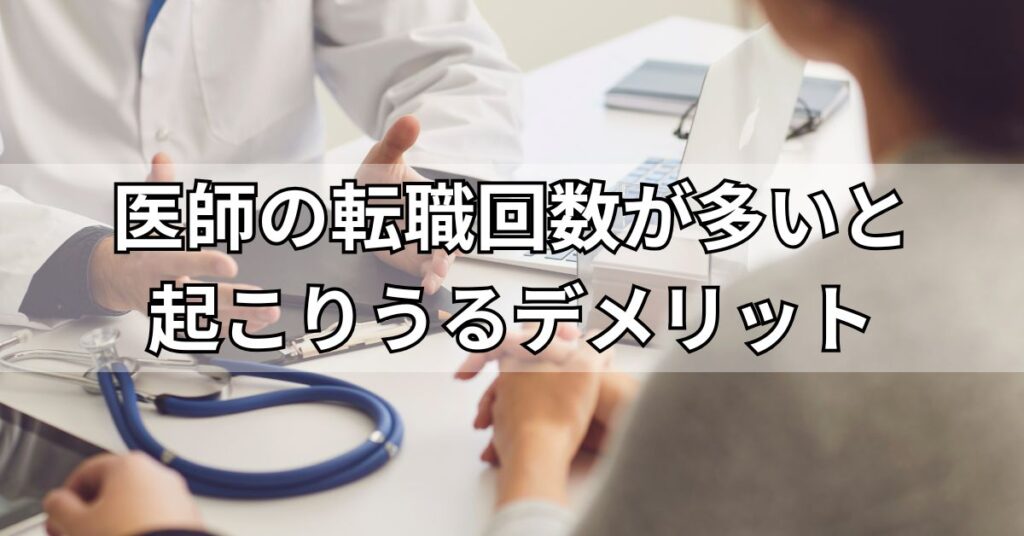
転職を経験する医師は多いですが、回数が多いとデメリットが起こる可能性があります。ここでは、主なデメリットを見ていきましょう。
問題があると見なされる可能性がある
医師の転職回数が多いと、採用担当者から「何か問題があるのでは」と見なされ、採用において不利になることがあります。特に4回以上や、1~2年ごとの転職を繰り返している場合は注意が必要です。
ただし、妊娠・出産や家族の事情など納得できる理由がある場合は、転職の多さが必ずしも大きなマイナスにはなりません。面接時に転職回数について質問される可能性もあるため、きちんと説明できるよう準備しておくことが大切です。
退職金への影響が懸念される
医師が頻繁に転職を行う場合、退職金が減額される可能性があります。退職金は一般的に、同一の医療機関での勤続年数に応じて支給額が決まります。
短期間で転職を繰り返すと十分な在籍年数に達せず、結果として受け取れる金額が大幅に少なくなることもあるでしょう。
さらに、小規模な病院では退職金制度が整っていないケースもあり、転職のたびにその影響を受ける可能性があります。退職金に不安がある場合は、自分自身で資産形成や老後資金の準備を進めることをおすすめします。
医師の労働が過酷になる背景
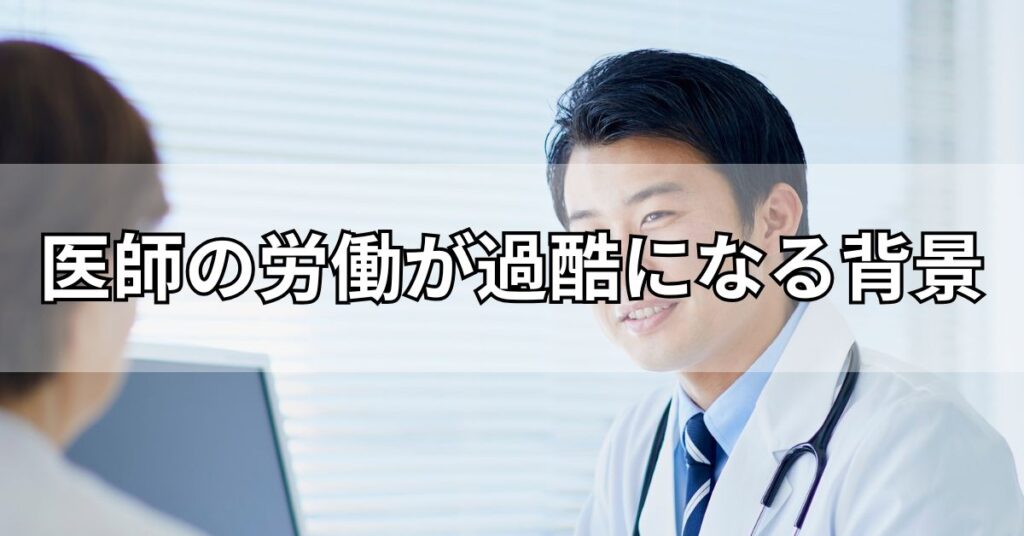
過酷な労働環境を理由に転職を考える医師も多いものです。ここでは、なぜ医師の仕事が過酷になりやすいのかについて解説します。
勤務が不規則で長時間になりやすい
主な要因の一つとして、勤務が不規則で長時間になりやすいことが挙げられます。医師は救急対応や患者ケアのため、昼夜を問わず働く必要があります。
特に救急医療や専門性の高い診療科ではオンコール対応が頻繁で、プライベートの時間を確保するのが難しくなりがちです。日本では交代制勤務が十分に普及しておらず、一人ひとりの医師にかかる負担が大きいのが現状です。
たとえば心臓外科医が深夜に緊急手術を求められ、数時間にわたって高い集中力を維持しながら対応するケースも珍しくありません。現場では働き方改革が進められているものの、多くの医師が依然として厳しい労働環境に置かれています。
患者対応に神経を使う場面も多い
医師の労働が過酷になる背景の一つに、患者対応に神経を使う場面が多いことが挙げられます。医療ミスや説明不足による誤解が発生した場合、患者からのクレームや訴訟に発展することもあり、常に緊張感を持って対応しなければなりません。
忙しい外来や急患対応の合間に、全ての患者に丁寧な配慮を行うのは難しく、その結果、疲労やストレスが蓄積しやすくなります。
近年は、患者とのコミュニケーションを支援する体制が病院内で整備されつつありますが、根本的な改善にはまだ至っていないのが現状です。医師が心身の健康を犠牲にしてまで患者対応を続ける状況を、構造的に見直すことが求められています。
勤務地が変わることが多い
医師の労働環境が過酷になる要因の一つに、勤務地が変わることが多いことが挙げられます。大学病院や医局に所属している場合、数年ごとの異動が一般的です。
たとえば、家族と暮らす地域から遠く離れた病院へ転勤となれば、通勤時間の増加や家庭生活への影響が避けられません。実際に、勤務地への不満が理由で医局を離れたというケースもあるようです。
勤務地に強い希望がある場合は、異動や転勤が少ない病院を選んで転職することが、働きやすい環境を手に入れるための有効な選択肢となります。
転職を考えるべき医師の特徴
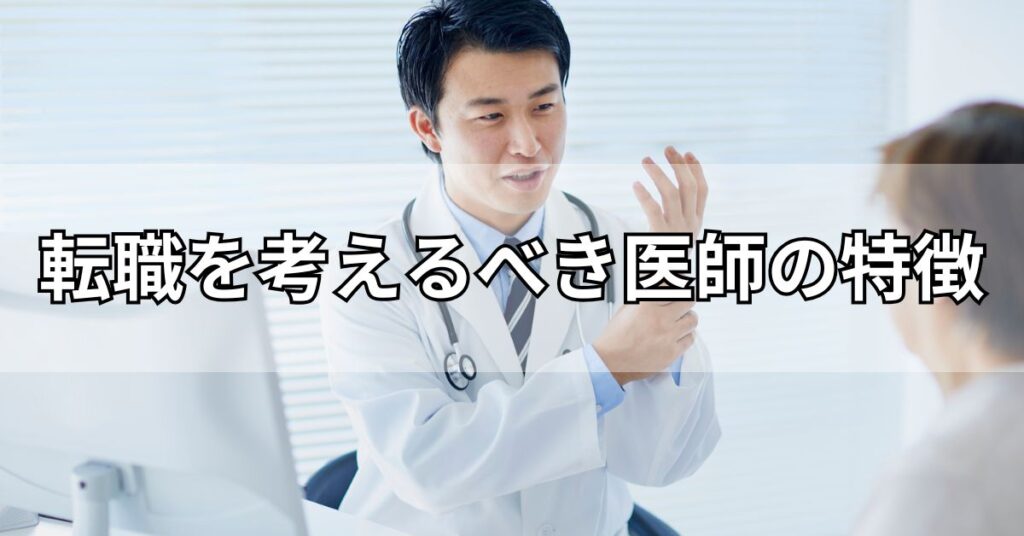
ここでは、転職を考えるべき医師の特徴について解説します。
精神的・身体的に限界を感じている
精神的または身体的に限界を感じている医師は、できる限り早く転職を検討するべきです。医師の職場環境は非常に過酷で、他の職種では経験しにくい高いレベルのストレスにさらされる方もいます。
「患者のために頑張らなければ」「今辞めると周囲に迷惑がかかる」といった思いから無理を続ける医師も多く見られますが、心身が疲弊した状態では質の高い医療を提供することが難しくなります。
まずは自分自身の健康を守ることが大切です。転職によって心身の状態が回復すれば、より良い診療環境で活躍できる可能性も広がるでしょう。
仕事量の割に給与が低い
仕事量に対して給与が見合わないと感じる場合は、転職を前向きに検討するべきです。特にサービス残業が多い職場では、労働量に対して報酬が不十分だと感じると、モチベーションの低下につながる可能性があります。
適正な報酬を得ることは、医師が長期的に質の高い医療を提供し続けるためにも重要です。転職によって新たな環境での挑戦が可能になり、より良い条件の職場に出会える可能性が高まります。
現在の収入に不満を抱えている医師は、給与アップの可能性も含めて、転職先の選択肢を検討してみるとよいでしょう。
契約時の条件と現場にギャップがある
契約時に提示された条件と実際の勤務環境や業務内容に大きなギャップがある場合、医師は転職を検討すべきです。想定していた労働環境と異なる状況で働き続けることは、精神的・身体的なストレスの蓄積につながりかねません。
たとえば、契約では当直が月2回とされていたのに、実際には月4回以上を求められるようなケースでは、プライベートの時間が確保できず大きな負担となる可能性があります。
こうした契約と実態のギャップに直面した場合は、まず職場と誠実に話し合いを行い、改善を求めることが重要です。それでも解決が難しい場合は、自身の健康や生活を守るためにも、転職という選択肢を視野に入れるべきでしょう。
なお、勤務医にとっては残業代の扱いも大きな問題です。年俸制や固定残業代制など制度の違いによって取り扱いが変わるため、理解を深めておくことが必要です。
参考:医師(勤務医)の残業代請求|年俸制・固定残業代制の場合も解説
転職が多くても好印象を与える理由の伝え方
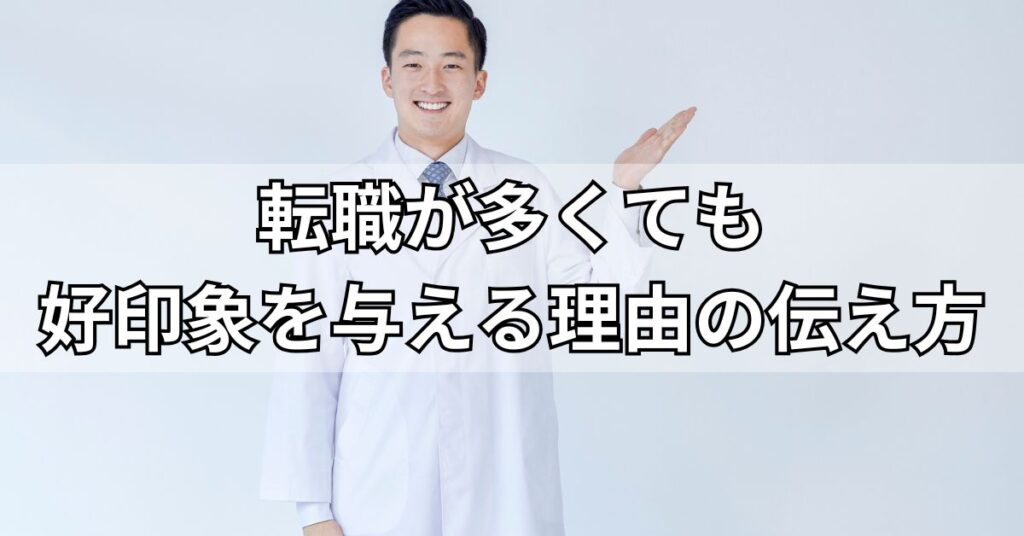
転職が多くても、伝え方次第で採用担当に好印象を与えることができます。ここでは、3つのポイントについて解説します。
転職歴をネガティブにせず好意的に伝える
転職が多い場合でも、理由をネガティブにせず前向きに伝えることで、採用担当者に好印象を与えることができます。前向きな説明は、向上心や成長意欲のある人材として評価される可能性を高めます。
たとえば「新しい環境でスキルを高めたい」や「より専門性を高めるために挑戦した」といった表現は、積極的な姿勢を伝えるのに有効です。
前職に対する批判は避け、あくまで自分の意欲や将来像を軸に話すことで、転職歴をプラスに変えることができるでしょう。
正当な事情があれば転職理由は伝えてよい
正当な事情がある場合は、転職理由を率直に伝えることで信頼感を与え、好印象につなげることが可能です。
ハードワークによる体調面の不安や、医療機関との理念の違いといったやむを得ない理由であれば、採用担当者も納得しやすく、マイナスに評価されることは少ないでしょう。
特に診療方針の違いによる転職であれば、応募先の方針と自分の価値観が一致している点を強調することで、前向きな理由として伝えられます。
これまでの改善の努力や、今後の目標、そして応募先でどのように貢献できるかをアピールすることもおすすめです。
人間関係を転職理由にする際は注意が必要
人間関係を転職理由にする際は、伝え方に注意しないと採用担当者にネガティブな印象を与える可能性があります。
人間関係の問題は多くの職場で起こり得るため、「同様の状況があればまた辞めるのでは」と不安を持たれることがあるからです。前職の関係性を一方的に否定するような発言は、協調性に欠けると判断されかねません。
そのため、「当時の経験から何を学んだか」「自分にどのような課題があったか」といった点を前向きに捉え、成長の機会として説明することが大切です。誠実な姿勢を示すことで、採用担当者に好印象を与えることができるでしょう。
転職回数が多い医師でも成功させるポイント
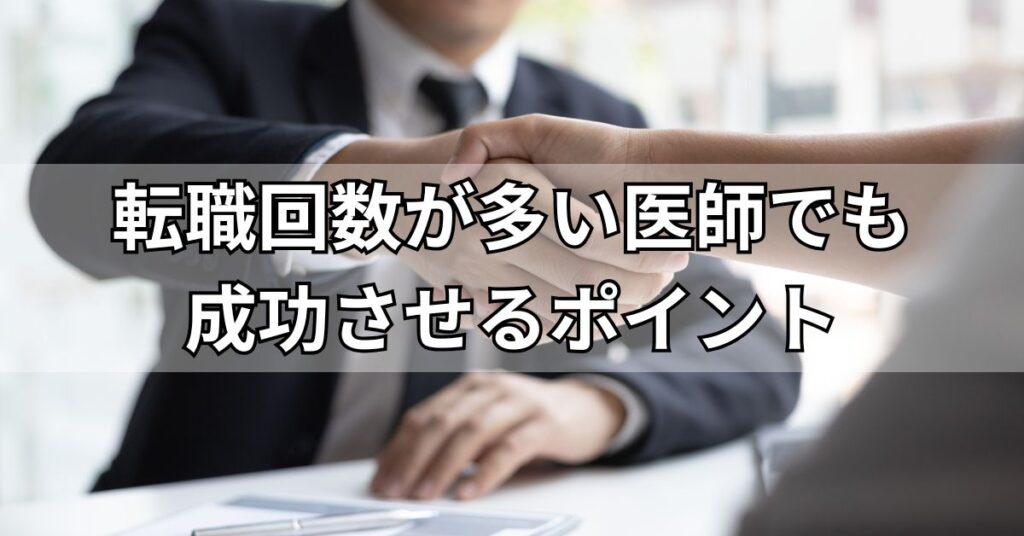
転職成功のための3つのポイントは、以下のとおりです。転職を考えている医師はぜひ参考にしてみてください。
長く働く意思と貢献意識を具体的に示すことが重要
転職を繰り返した医師は、面接で定着意欲と貢献意欲を明確に伝えることが重要です。これにより採用担当者に安心感を与え、採用の可能性を高めることができます。
転職回数が多い場合、「また短期間で辞めてしまうのでは」と懸念されやすいため、面接では「今後5年、10年のキャリアビジョン」を具体的に語り、長期的な勤務意欲をしっかりと伝えることが求められます。
また、自分がどのように職場に貢献できるかを具体的に話すこともポイントです。事前に応募先の理念やビジョンを調べ、それに合致した内容を準備しておきましょう。
転職の軸を明確に持つ
転職回数が多い医師でも転職を成功させるには、明確な転職の軸を持つことが不可欠です。自身のキャリアプランや人生設計に合った職場を見つけるためには、「自分が何を最も重視するのか」という基準をはっきりさせる必要があります。
転職の軸が定まっていないと、目先の条件や周囲の意見に流されやすくなり、短期間で転職を繰り返すリスクが高まります。
軸を決める際は、譲れない条件を1つに絞り、そのほかの希望条件を2~3点に整理しましょう。キャリアビジョンやワークライフバランス、将来の働き方を踏まえて、自分にとって最も重要なポイントを明確にしてみてください。
交渉可能な条件を整理しておく
転職回数が多い医師が転職を成功させるには、交渉可能な条件をあらかじめ整理しておくことが重要です。交渉では、すべての希望が通るとは限らず、相手側も妥協点を模索する場面が少なくありません。
そのため、譲れない条件が曖昧なままだと、転職後に「妥協しなければよかった」と後悔する原因になります。
給与、勤務時間、オンコールの頻度などについて、あらかじめ譲れない条件と妥協可能な条件を区別しておくと、交渉がスムーズに進みます。明確な判断基準を持つことで、不必要な妥協を避け、理想に近い転職を実現しやすくなるでしょう。
医師におすすめの転職エージェント
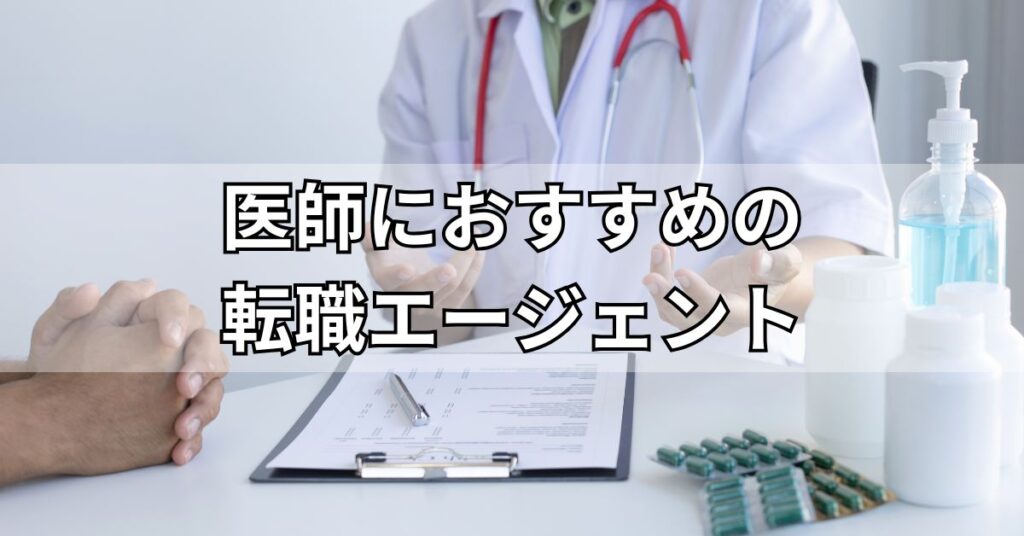
ここでは、医師の転職サポートが充実しているおすすめの転職エージェントを3社紹介します。それぞれの特徴やおすすめのポイントを参考にして、自身に合ったエージェントを見つけましょう。
医師転職ドットコム

- 常勤・非常勤の求人が多く医師の多様な働き方に柔軟に対応できる
- 医師会員数70,000名以上
- コンサルタントによる質の高いサポートの提供
医師転職ドットコムは、常勤・非常勤の両方に対応した幅広い求人を取り扱っており、医師の多様な働き方に柔軟に対応できるのが特徴です。
公開求人に加えて非公開求人も豊富に用意されており、医師一人ひとりのニーズに合った求人を提案することが可能です。取引先医療機関数は19,000件以上で大学病院からクリニック、製薬企業まで多彩な選択肢がそろっています。
また、丁寧な対応と迅速なレスポンスが好評で、多くの医師から高く評価されています。医師会員数は70,000名以上であり、信頼性と実績も申し分ありません。
さらに、サイト上では医療業界の最新動向やキャリア形成に役立つ情報を随時発信しており、転職支援にとどまらず長期的なキャリア設計をサポートしてくれる点も魅力です。
| 医師転職ドットコムの基本情報 | |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社メディウェル |
| 公式サイト | https://www.dr-10.com/ |
| 求人数 | 30,540件(2026年1月26日現在) |
| 取り扱い科目 | 【内科系】内科、総合診療科、消化器内科、呼吸器内科、循環器内科など 【外科系】外科、消化器外科、呼吸器外科、心臓血管外科、血管外科など 【その他】眼科、皮膚科、耳鼻咽喉科、精神科、心療内科、放射線科など |
関連記事>>医師転職ドットコムの評判・口コミ
Dr.転職なび

- 医療経営士資格を持つコンサルタント
- 豊富な求人情報と非公開求人
- 分業制コンサルによる効率的かつ高精度な求人
Dr.転職なびは、医師担当と求人担当を分けた分業制のコンサルティング体制を採用しています。医師対応と求人管理の専任担当者が連携することで、迅速かつ丁寧なサポートが可能です。
また、医療経営士の資格を持つコンサルタントが在籍していることで、転職先を経営の視点から深く理解し、専門知識を活かした提案を行ってくれます。
さらに、全体の9割以上が非公開求人となっており、他では見つかりにくい好条件の案件と出会える可能性があります。求人情報は日々更新されているため、常に新しい情報をチェックできる点が魅力です。
オンラインでのキャリアカウンセリングにも対応しているため、忙しい医師でも時間を有効に使いながら相談が可能です。まずは相談だけでも、視野を広げるきっかけになるでしょう。
| Dr.転職なびの基本情報 | |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社エムステージ |
| 公式サイト | https://tenshoku.doctor-navi.jp/ |
| 公開求人数 | 非公開(2026年1月26日現在) |
| 主な取扱職種 | 一般内科、一般内科(訪問診療) 呼吸器内科、循環器内科 消化器内科など |
関連記事>>Dr.転職なびの評判・口コミ
リクルートドクターズキャリア

- 専任アドバイザーによる手厚い支援
- 2,000万以上の高収入案件を豊富に取り扱っている
- 40年以上の転職支援実績による信頼性
リクルートドクターズキャリアは、医師転職に精通したアドバイザーが、丁寧なヒアリングを通じて個々のニーズを深く把握します。求人紹介だけでなく、条件交渉や面接対策まで一貫してサポートするエージェントです。
リクルートグループの40年以上にわたる実績に基づいたノウハウと、全国規模のネットワークを活かし、幅広い診療科に対応しています。
年収や勤務条件など、医師ならではの希望にも柔軟に対応し、キャリアプランやライフステージに合わせた求人提案が可能です。夜21時までの電話対応やオンライン面談など、忙しい医師でも利用しやすい体制が整っています。
秘密厳守の方針が徹底されているため、現職に知られずに転職活動を進めたい医師からも信頼されています。
| リクルートドクターズキャリアの基本情報 | |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社リクルートメディカルキャリア |
| 公式サイト | https://www.recruit-dc.co.jp/ |
| 公開求人数 | 非公開(2026年1月26日現在) |
| 主な取扱職種 | 一般内科・総合内科、消化器内科 循環器内科、呼吸器内科など |
関連記事>>リクルートドクターズキャリアの評判・口コミ
転職回数が多い医師に関するよくある疑問
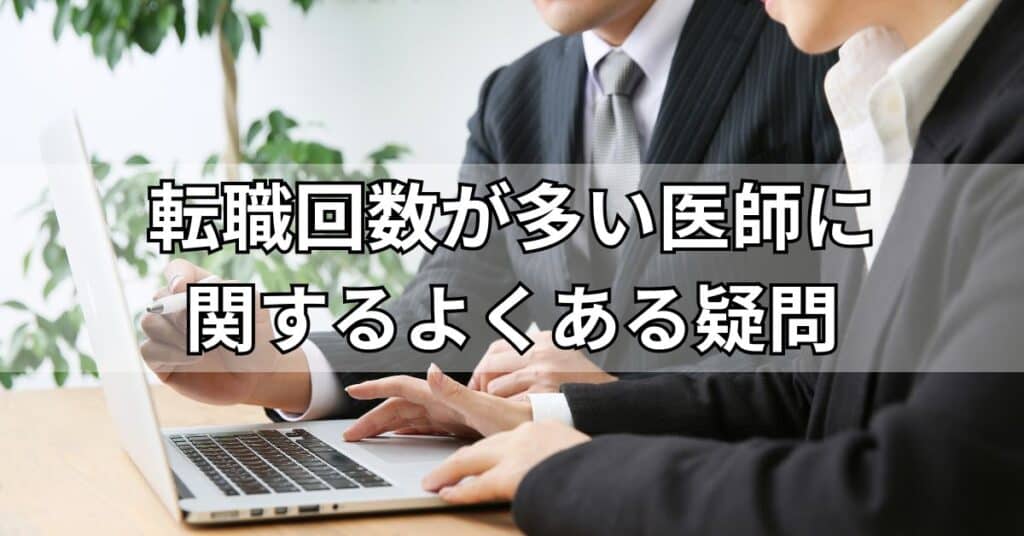
最後に、転職回数が多い医師に関する主な疑問をQ&A形式で解説します。
医師は転勤が多いですか?
医師の転勤頻度は、所属形態によって大きく異なります。医局に所属している医師は転勤が多く、病院と直接雇用契約を結んでいる医師は転勤が少ない傾向があります。
医局所属の医師は、人事システムに基づき大学病院や関連施設へ派遣されるのが一般的です。
一方、医局に属さない医師は病院と直接契約しているため、勤務先が安定し、異動の必要性が少ないのが特徴です。医局にいれば転勤は避けにくいですが、そうでなければ長く同じ職場で働ける可能性が高いといえます。
医師のよくある退職トラブルは?
医師は専門性が高く代わりがきかないため、退職を申し出ると職場から強く引き留められるケースが多く見られます。実際に多くの医師が、退職の意向を示した際に上司や同僚から強い慰留を受けています。
中には、院長や同僚が引き継ぎに非協力的で患者の担当を円滑に移せず苦労したり、引き継ぎマニュアルを一人で作成せざるを得なかったりといったトラブルも少なくありません。
こうした問題には、早めの意思表示や丁寧な引き継ぎの準備、必要に応じて弁護士など専門家への相談が効果的です。
医者はどうして病院を転々とするのか?
医者が病院を転々とする主な理由には、労働条件の改善やキャリアアップ、新たな環境での挑戦などがあります。長時間労働や精神的な負担が多い医師は、転職率が高い傾向にあります。
さらに、職場の価値観や医療方針が自身と合わない場合には、やりがいを求めて別の職場を選ぶことも珍しくありません。
たとえば、地方病院で過酷な勤務に耐えきれず、休日出勤や深夜残業の少ない都市部の病院へ転職するケースも多く見られます。病院を渡り歩く理由はさまざまですが、どれも自分のキャリアや働き方を真剣に見つめ直した結果といえるでしょう。
医者が突然クビになったらどうすればいい?
医師が解雇される主な理由は、主に以下のとおりです。万が一にも解雇された場合は、冷静に対処し、必要な手続きを踏むことが重要です。
- 業績不振
- 職場の人間関係
- 医療ミス
- 患者とのトラブル
解雇を通知されたら、すぐに「働く意思があります」と書面で伝え、業務指示を求めましょう。続いて、労働基準法に基づいて解雇理由証明書の提出を求めることが大切です。
理由が明らかになれば、今後の対応に役立ちます。もし双方の認識に食い違いがある場合は、話し合いによって解決策を見つけられる可能性もあります。
交渉がまとまらないときは、労働審判や訴訟を検討することも視野に入れましょう。
医師が転職する年齢は?
医師の転職は主に、30~40代が多い傾向にあります。30代は専門医の資格取得や結婚・出産など、ライフイベントが重なる時期であり、スキル向上やワークライフバランスを求めて、初めて転職するケースが多く見られます。
一方で、40代になるとさらなるキャリアアップや専門性の追求を目的に転職する医師が増えてきます。
年齢が上がるにつれて転職回数も増える傾向があり、60代以上では複数回の転職経験を持つ医師も珍しくありません。キャリアの段階ごとに変化するニーズや目標に応じて、転職のタイミングを見極めることが重要です。
実際に医師を辞める割合はどの程度ですか?
医師が実際に退職する割合は、厚生労働省のデータによると年間約5.1%※とされています。医師は一般に安定した職業と見られがちですが、実際には長時間労働や重い責任、対人関係によるストレスなど、多くの負担を抱えています。
医療現場では人手不足が深刻化しており、限られた人数での長時間勤務によって、心身の健康を損なうケースも少なくありません。
また、責任の重さに見合わない給与や手当を理由に、より良い条件を求めて職場を変えたり、開業や異業種への転職を目指したりする医師もいます。医療現場の持続的な安定には、働き方改革とサポート体制の充実が不可欠です。
まとめ

医師の転職回数について解説しました。医師は他の職種に比べて転職回数が多い傾向にありますが、その理由が明確であれば転職活動で不利になることはほとんどありません。
長く働く意志や転職理由をしっかり伝えることで、納得のいくキャリアを築くことができます。不安がある場合は、転職エージェントなどの専門家に相談してみるのも有効な方法です。